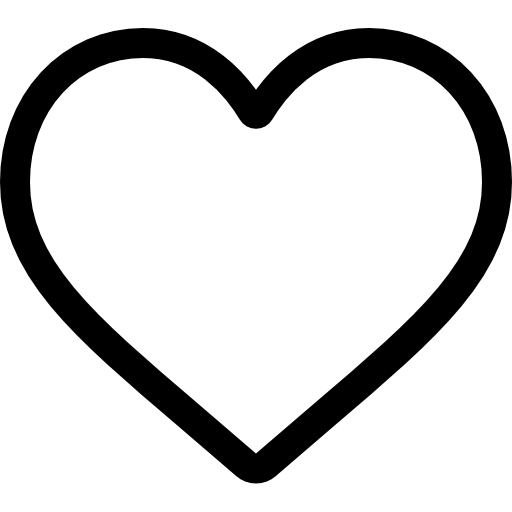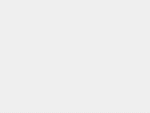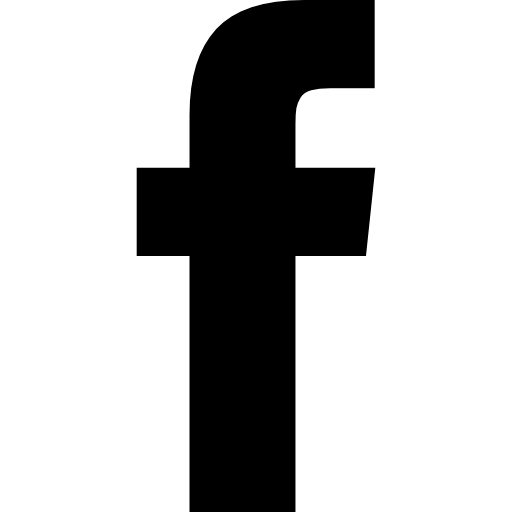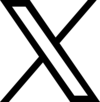渡航前の医療
海外赴任の準備/精神科医の立場からみた子供たちの異文化適応
この記事で書かれていること
はじめに
しばしば親は子供の資質について(良い方へ)誤解をしており多くを望み過ぎている。たいていの親は、親ができないことでも子供はできると信じている。たとえば海外への赴任に子供を帯同する場合も、「大人は(現地の)言葉をすぐには話せないけれど子供は難なく覚えて話す」とか「大人は(現地に)馴染みにくいけれど子供はすぐ馴染める」などと考えがちである。しかし、実際には子供にも大人におけると同様にあるいはそれ以上に多くの困難が生じている。子供にとっては大人以上に海外は見知らぬ土地であり、馴染みでない新しいことに対処する方法を大人以上に知らない。
また、海外に滞在すると、特に英語圏に滞在した場合、親も周囲も語学の習得を子供に期待するが、この点にも多くの誤解がある。親は「子供にとっての海外滞在」=「子供は海外という外国語圏にも居住し自宅という日本語圏にも居る」と解釈しがちであるが、実際のところ子供は「外国語圏にも十分には居ない、日本語圏にも十分には居ない」という経験をする可能性があり、外国語を覚えるより先に日本語を忘れるということさえも起こり得る。本稿では精神科医からみた子供たちの海外転地の問題と適応について述べてみたい。
子供たちの側から見た負荷としての海外赴任
ところで精神医学的には、子供にとっての「海外転地」はいくつかの軽度のストレス(心理的負荷)が複合されたものである。現在もっとも一般的な診断基準の1つであるDSM-Ⅳにおいて、慣れ親しんだ環境からの決別、親密な友人や遊び仲間との別れ、顔見知りの近隣の消失、新しい環境への適応、言葉の壁などはいずれも軽度のストレスとして定義されている。思春期以降の青少年には恋人との別れという中程度のストレスがあるかもしれない。しかし、いずれにしろ、子供たちは軽度以上のストレスの加算された結果として中程度以上の心理的負荷を抱えて転地することになる。ストレスに対して人はさまざまな防衛――心が傷つかないようにする工夫――を試みるものである。成人と同じく子供にとってストレスは時として大きな心的外傷の原因となりうる。成人と異なる点は、正常な発育をしている場合でも年齢が小さいためにより原始的な、言ってみれば病的な防衛が出現しがちなことである。たとえば、「慣れ親しんだ環境から離れ、親密な友人と別れること」について、率直に心の傷を表現し両親に不満を訴えたり友人と泣きあったりするとともにさまざまな防衛をする。比較的成熟した防衛である合理化や知性化をし、「より広い世界の人々と知り合う」「寂しいのはしばらくだけ」と納得する場合もあろう。下痢をしたり熱が出たりという身体化をすることも年少の児には多いだろう。ときには急に子供っぽくなったりそれまでなかった指シャブリや爪噛みの習慣が出現したりすることもあろう。さらに、反動形成や投影、逆転といったいささか病的な防衛となることもありうる。つまり、友人と別れるのがつらい場合、実際はその友人がよくない友人だったと訴えたり、友人が寂しがって一緒に来ると言っているなど大人からみると嘘ととれることを言い出したり、逆に友人を些細なことでひどく憎み始めたりするような防衛である。この場合は外界について子供が考えていることが事実と噛み合わなくなってくるのでしばしば病的な精神状態を呈してくる。従来は子供には大人のような「抑うつ」や「神経症的反応」はおこらないとされていたが、近年では大人に起こる精神症状は頻度こそ異なるものの基本的にすべて存在するであろうという立場を精神科医はとりつつある。その上に発達障害や学習障害など年齢特有の精神医学的問題がある。
大人たちは海外赴任の心理的負荷を能動的に選択したが、子供たちは海外転地という心理的負荷をその養育者によって否応なく与えられる。この点で大人は子供の心理的負荷の軽減と理解、海外での適応に援助する責任があろう。
海外での適応
実際に海外に転地した場合、子供たちはさまざまな形の適応を試みる。およそ正常な適応を同化型、疎外型、境界型、統合型の 4つに分けて説明する(表1)。個々人の適応ははっきりとこの4型に分かれる場合もあるし、また、はっきりと分類できない場合もある。
第1に同化型は、現地の行動規範や文化の枠組みを内在化(自分自身のものとして取り込むこと)し、それに基づいて行動している群である。同化型の子供たちは、比較的長期に滞在し現地の言葉にも堪能で、いわば現地の文化を異文化ではなく自分自身の文化として感じている。欧米など先進国に比較的幼少時から長期に滞在し、教育の大部分を現地の教育システムで受けた子供にこの型が多い。家族も現地文化に肯定的で現地同化を心がけ、養育者も異文化接触度が高い。ホームパーティーにも現地の人が参加する家庭である。
第2に疎外型は現地に馴染めない群である。もちろん現地に小学校高学年以降に転地してきた当座は全員がこの群である。言葉が理解できず、周囲で何が起こっているのかさえまったくわからないわけで、結果として現地の社会からも疎外されている状態である。現地校に入学してもカリキュラムについていけず学校生活に適応できないでいる。欧米特に米国の教室ではbilingualの教師が副担任となるものの不自由であることは否めない。また、日本人学校に通学する場合もある。さらに疎外型のなかには単に疎外されているだけでなく、いつまで経っても現地の文化や生活に好きなところが見つからず、いささかでも同一化(現地にとけ込む)することを拒否する1群がいる。後進国に赴任し家族全員が現地にとけ込むことを拒否し、家族全員が現地の言葉をほとんど理解できない場合がこの典型であるが、それだけではなく先進国に赴任し親は子供に溶け込むことを期待し現地校に通学している場合にも、このような群は存在する。言葉が理解できるようになって授業には一応ついていけてはいるもののいつまでも現地の友人ができず現地の生活には馴染めず、家では日本のテレビ番組やビデオを見て日本人同士で交流する。現地の文化を嫌っている。いわば同一化拒否群である。帰国の日を逆算しては帰国に向けて準備を進めるばかりである。
| 表 1:海外での適応型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現地適応の型 | 児の年齢 | 滞在年数 | 家庭の教育方針 | 現地への適応 |
| 同化型 | 乳幼児、 低い | 長い | 現地への同化 | 良 |
| 疎外型 | 高年齢 小中学校以降 | 短い | 滞在時のみ | 積極的でない |
| 境界型 | 中年齢 幼稚園以降 | 短い | 滞在時のみ | 積極的でない |
| 統合型 | 高い 中学生以上 | 長い | 不定 | 比較的、積極的 |
第3に境界型は現地に馴染もうとし、言葉を学び、生活様式や行動様式を現地に合わせようとしてうまくいっていない群である。言葉は何とか話しているけれどニュアンスがわからない。ときどきジョークが通じず友人にからかわれる。現地校に通学しており現地の友人と遊ぶときには不自由はないが、しかし授業の進度が早すぎるように感じ、科目特有の言葉にはついていけない。しばらく滞在し現地校に通い馴染んではきたものの思い通りにならないことが多い。幼稚園以降海外転地した場合は例外なくこの型を経過して同化型や統合型に移行していく。誰もがはじめから言葉が話せるわけではないし、生活様式や行動様式を理解できるわけではないからである。現地の友人と同じように振る舞いたいけれど振る舞えないから日本に帰りたい。現地の友人と遊びたいけれど自由に遊べないから日本人の友人と遊びたい。いずれ日本に帰国するが現地に滞在する間はできるだけ現地に同化しようとしているのだが、家族もまだ慣れておらず日本人といる方がらくである。
最後に統合型は、長期に現地に滞在し、学年も進んでおり自我や自尊心などの抽象的概念も理解できる年齢で生じる型である。現地の生活に行動面では適応しており、言語的にもすでに問題なく現地校の授業も容易に理解できている。体を使った遊びをするのみならず対等に議論をし、年齢相応の抽象的葛藤について打ち明け話し合い悩みを共有する現地の友人がいる。さらにその中で自国の文化や行動規範との違いをも理解しており、自国の文化、社会に対しても現地の文化、社会に対しても長所と短所を自分なりの言葉でいささか客観的に言うことができる。自他の違いを認め、事に当たって是是非非で対処するという個人として成熟した態度を採る子供たちであり、自分の意見をはっきりと主張する。この「異なる文化を認める」「個人主義的態度」は、実際のところ島国育ちの日本人が従来もっとも苦手としてきた態度といっても過言ではない。そのために周囲の日本人の大人からときには変わった子や生意気な子として扱われることもあろう。
以上適応の型を大きく4型に分類してみたが、これらの型は海外転地後時を追って変化していくものである。さらに言えば、ある子供がある1つの型にとどまり続けることはむしろ少なく、現実にはいくつかの型の混合型や移行型の方が多い。
帰国後の適応
海外での適応も大きな問題であるが、子供たちにとっては帰国後の適応も更に大きな問題となる。海外では適応がうまくいかなかった場合も「(ここは仮の生活で)日本に帰ったらちゃんとやれるから」「(少し長いバケーションのようなものだから)成績にはこだわらない」として親子ともに納得することもできる。しかし、日本での不適応は親にとっても子供にとってもしばしば人生の躓きとして実感され、将来に対する不安が増し大きな心理的負荷となる。さまざまな形で適応しようとして子供は必死の努力をすることになる。
帰国後の適応の型を3型(表2)に分類して説明する。まず、抑圧削除型である。現地の文化、社会の中で身につけたもののうち日本の文化や社会において受容されにくいものを抑圧し、削り取って適応する型である。日本の文化、社会は「皆と違うこと」を受容しにくいため、この場合かなり多くの部分が「日本と異なる」ものとして削除抑圧されることになる。たとえば実際英米圏で生活した帰国子女ではしばしば認められることであるが、現地では親よりも流暢な発音で現地の友人と英語で話していた子供が日本に帰ってきてしばらくするとまったくの日本語英語しか話さなくなる。「(皆と異なる)現地の英語」を削除抑圧したのである。実際に英語の発音を「気取っている」などといじめられたりしなかった場合でもこのような形での適応は生じてくる。子供たちは現地で身につけたものの中で日本文化に合わないものを鋭く認知ししばしば抑圧あるいは削除することによって適応しようとする。この型の適応は、現地での適応が疎外型、境界型だった場合に比較的おこりやすい。現地での適応が疎外型や境界型だった子供たちは現地で身につけたことに対して警戒していることが多い。したがって不適切なものとして抑圧削除しやすい傾向がありがちである。しかしながら部分的にはこの型の適応は日本での再適応の過程でどの子供にも大なり小なり起こってくる適応の型であるともいえる。
次に追加保持型は、海外で身につけたものに日本における再学習の結果を追加することにより、できるだけ周囲との摩擦を起こさないように適応を図る一方、海外で身につけたことを抑圧しつつも保持しつづけようとする型である。海外で身につけたものを隠す、日本社会に自分の側が変わり適応しようとする点では抑圧削除型と変わりがないが内面的には海外の文化社会の良い面を保ち続けようとしている。たとえば、転校した学校では日本式の英語の発音をしていても、週末の帰国子女学級では本来の現地の発音で話すような子供たちである。
3番目の適応型は自律型で、いわばマイウエイとでもいう型である。海外で育ったことは自分の個性に過ぎず取りたてて言うべきことでもないし、ことさらに自分を抑えて日本の社会に合わせることもないと考えて独自の規範で行動している。比較的年長の子供たちで、周囲もそのような適応を許すような環境であることが多い。子供の側には自国の文化や社会に対して是是非非で対応する成熟度が必要であるし、同時に受け入れる側にも帰国子女を特別視せずまた多様な文化の存在を認める環境であることがこの型の基盤には要求される。比較的年長たとえば大学生くらいになると帰国当初からこの型で適応することがあるが、高校生以下の年齢であると他の型を経由してこの型に至ることもある。いずれにしろ、海外での適応の諸型同様これら3型は純粋な型で出現することは少なく、さまざまな形で混合して出現することになる。
| 表2:帰国後の適応型 | ||
|---|---|---|
| 帰国後適応の型 | 児の年齢 | 滞在期間 |
| 抑圧削除型 | 低、中学齢 | 比較的短い |
| 追加保持型 | 中学齢 | 不定 |
| 自律型 | 高年齢 | 中から長期 |
日本の教育と英米の教育の特徴
海外転地をした場合、欧米圏以外では多くの父兄は日本人学校あるいはインターナショナルスクールに子女を通学させることになろう。一方欧米圏に赴任した場合は子供たちを現地校あるいはインターナショナルスクールに通学させることが多い。したがって、ここでは、現地校およびインターナショナルスクールに通学させた場合と日本の学校の教育の基本的理念、方針の違いについて述べる。日本も欧米圏の社会も子供を将来その社会にとって有用な公民としようとして教育する。したがって教育方針の相違はとりもなおさず社会が求める良き公民像の違いでもある。英米圏の「良き公民(大人)」は必ずしも世界共通の「良き公民」、日本で求められる「良き公民」とは限らない。いずれが正しいかということではなく相違があるということを親は理解しなければならない。
日本の社会は従来「協調性」や「忍耐」、「従順」を「良き公民」の徳質としてきた。したがって日本の教育の構造は上記の徳質を養成するように構成された。結果として 1. 学年制による画一性 2. 系統性を持った教科の縦割り授業 3. 教師中心の一斉授業という特徴をもつことになった。一方、欧米の公民の理想は自立した個人である。つまり他者と異なる個々人固有の意見をもつとともにそれに対する責任をとり、他者の意見や自由もまた尊重することができる個人である。したがって、教育の構造上の特徴もその理念に従っており、 1. 各教師の裁量に基づくクラス毎に異なる授業 2. 課題追求型授業 3. 生徒中心の個別的授業となる。欧米型の授業では同一の教科であっても各学校、ときには各クラスで教えている内容がまったく異なるということがありうる。子供たちの成長に合わせて自分たち自身で課題追求していけるように教えていく、とでも表現したらよいのだろうか。すなわち子供たちはどのようにすればより効果的に課題を追求できるか、そのノウハウの指導を受ける。たとえば図書館の使い方、コンピューターの使い方、インターネットでの検索法などである。子供の年齢に合わせて共通しているのはこうした「学習の仕方」の進度だけであって、何を課題にするかは各教師によって異なってくる。学習グループの生徒の学力や興味に合わせて課題が決定され授業がおこなわれていく。
こうしてみると、親の赴任と帰国に伴い子供たちはずいぶん違うところから違うところへ行ったり帰ったりするわけである。社会や文化の基本的なあり方の違いはやはり日常的な学校生活のなかにも現れてくる。子供たちの海外滞在時および日本帰国時の適応の問題は、たしかに個別的な子供たちの問題であるがそれ以上に、2つの異なる文化の「良き公民」像の差の問題なのである。
現在、日本の教育は大きな転換期を迎えている。上記に述べた日本の教育の構造上の特徴は現在もなお基本的には変わってはいない。しかし一方では1996年以来中央教育審議会は再三「国際理解教育」を強調している。これは、「同一性」「協調性」よりも「多様性」「自己の確立」を志向する内容である。 1. 広い視野をもち異文化を理解すると共にこれを尊重する態度や異なる文化をもった人々と共に生きて行く素質や能力の育成を図ること、 2. 国際理解のためにも、日本人としてまた、個人としての自己の確立を図ること、 3. 国際社会において、相手の立場を尊重しつつ自分の考えや意思を表現できる基礎的な力を育成する観点から外国語能力の基礎や表現力などのコミュニケーション能力の育成を図ること、以上の3点を骨子としている。こうした理念が額面通りであれば、これは日本の教育の基本的方針の大転換であり、欧米型の教育方針、良き公民像へのシフトを意味することになろう。
日本の教育が上記の方針に従い変化していくとすると、欧米の教育構造の特徴に近づいていくことになる。その結果、海外転地時、日本帰国時の適応が容易になる可能性はある。しかし異文化への適応という課題が今後も大人にとってと同様子供にとっての少なからぬ心理的負荷であることは変わらないであろう。
精神医学の先進国に子供を伴って赴任した場合の例外的なこと
最後にいささか特殊な話題であるが、精神医学の先進国たとえばアメリカ合衆国などに子供を帯同する場合に例外的に起こりうることを付記する。精神医学の先進国では乳幼児検診や学校検診において身体の障害のみでなく、部分的な知的発達障害や情緒的発達障害など精神発達上の障害をも詳細に検査する。この場合日本の乳幼児検診や幼稚園、学校検診では問題にならなかったことを障害として指摘される可能性がある。精神医学の一専門分野として乳幼児精神医学や小児精神医学、児童精神医学、思春期精神医学などの確立している欧米ではときに親からみればないはずの障害を指摘されることになる。たとえば「ただ落ち着きのない子」と思っていたのに「注意欠陥多動性障害」児として特殊教育を受ける必要があると宣告されることになる。親はこの診断に対してそんなはずはないと否認をしたり、あるいは大袈裟に受け取って早期発見できなかったと悔やんだり、さまざまな反応をしつつ子供の「障害の宣告」の事実に向き合っていく。そして特殊教育クラスのなかで次第に子供は落ち着きをみせ教育や治療の効果が認められるようになると、親も事実を受け入れ適応していく。この場合の帰国後の問題は日本において同等の医療や教育を探すことが困難なことである。このようなことは例外的なこととはいえ稀ではないので、一応適応の問題として付記した。なおこの場合に教育機関や医療機関の指示に従い子供のために制限期日以内に精査や治療を進めていかないと親が児童虐待(養育責任の放棄)として告発されて、留置、裁判の上国外退去処分を受ける可能性のある居住地もあるので十分配慮したい。
実際の症例
実際の精神科帰国子女外来には、帰国子女がさまざまな適応上の問題をかかえて受診する。著者の帰国子女外来における 2001年2月現在の外来受診者13症例についてまとめると11例が不登校(うち4例の摂食障害を含む)、1例がうつ病、1例が恐慌性(パニック)障害である。不登校に関していうと、1997年文部省は従来の見解を変更し「不登校は病気ではない」と宣言し、あらゆる子供がなりうる適応上の問題と位置づけている。したがってこれによれば7例は不登校の診断のみで受診しているのでいわば適応上の問題のみで受診する場合が全体の63.6%を占めていることになる。これら7例のうち1例には契機となった客観的な重篤ないじめの事実があったが、他の6例では主観的な疎外感いわば仲間はずれ感ともいうべき感覚は存在したものの、客観的ないじめや疎外の事実はなく、むしろ友人がしきりに登校を誘う環境の中で引きこもっている。
以下で不登校、摂食障害、うつ病および恐慌性(パニック)障害について症例を挙げて説明する(ただし、各症例はプライバシー保持のため特定不可能な形に変更した部分がある)。
症例1 疎外型から抑圧削除型へ、診断名;不登校
13歳女子。2人同胞の長女第1子。満期安産初歩発語など発達上の問題を認めない。7歳小学校1年時渡米。10歳4年生で帰国。アメリカでは現地校に通学し、帰国時までESL授業(第2外国語としての英語)を受講した。友人はもっぱら日本人で帰宅後は日本の衛星放送テレビ、日本の漫画や本をみて過ごし、しばしば家人に日本に帰りたいと訴えた。帰国後は公立小学校に通学し親しい友人もでき活発に過ごした。その後一般受験で私立中学に入学した。入学後夏休み明けから次第に欠席が多くなり2年生になると連続して休むようになった。2年の夏休み明けからまったく通学できなくなり受診した。学校ではクラスメートによるいじめなどの客観的事実は認められず本人もないと言う。ただし、英語の先生と担任の先生がいやだとのことである。 本症例は米国に小学校1年時に渡航し、現地ではむしろ日本に帰国したがり英語学習や現地での適応に消極的でいわゆる疎外型として経過した。中学入学後親の勧めに従い英語検定試験を受験したが帰国の友人より2段階低い検定結果であった。公立小学校ではクラスの中位の成績であったが、私立中学校では成績も振るわず、英語の授業中に教師が「英語圏に居たのに」などというので次第に行きたくなくなった。本人もアメリカに滞在したことを「失われた時間」と感じており海外経験があるのにできないと言われ登校できなくなった。傷つきやすく不安が強いために自尊心が傷つけられる場に居られなくなったのである。
症例2 境界―同化型から追加保持型へ、診断名;摂食障害(無食欲型)
14歳女子。3人同胞の長女第3子。満期安産、初歩発語など発達上の問題を認めない。5歳でカナダに渡航し、11歳で帰国。キンダーガーデンから現地小学校と、一貫して現地の正規教育を受け、小学校3年からは週末に日本人補習校に通学した。カナダの現地校での適応は良好で成績も良く同胞中もっとも手のかからない子供として育つ。カナダでは現地の友人も多く兄達よりも現地の生活に融け込み、母からはまるでカナダで生まれ育った子供にみえた。父の帰任に伴って6年生で帰国し、私立中学を帰国子女枠で受験し合格した。その中学は比較的帰国子女を多く受け入れており容易に友人もできた。母からみると日本の学校にも難なく融け込んだように見えた。しかしボス的存在の同級生からなにかと競争相手のように扱われ、ある時「肉が嫌いな割に太っているね」と言われたことを契機にダイエットを始めた。強迫的に食事のカロリーや時間にこだわるようになり結局登校できなくなった。断続的な不登校と摂食上の問題が生じて3カ月後に受診。受診時 153cm、37kg。-15%を超える痩せ、基礎代謝-18%、一旦開始した月経の中断、明らかな痩せ願望を認め摂食障害、無食欲型と診断した。
本症例はカナダに幼稚園時に渡航し、現地での適応は同胞中もっとも良好で学業成績も良くいわゆる同化型に近い境界型であった。本人にとってはカナダの学校が学校のすべてでテレビ番組も娯楽も現地の子供と同じものを楽しんでいた。稀に現地の子供についていけないこともあったが気にしていなかった。日本の学校に戻りはじめて疎外感を味わい、本来の自己を抑圧し適応しようとしたが失敗し摂食障害として事例化したものである。
症例3 同化―統合型から自律型へ、診断名;うつ病
17歳男子、同胞2人第1子長男。初歩発語など発達上に問題はない。4歳で渡米し、現地のキンダーガーデンから現地校に入学し7歳で帰国。帰国後公立小学校に通学した。日米ともに友人も多くよく遊ぶ活発な子供であった。10歳で再び異なる地方ではあるが渡米し、現地校に通学すると同時に週末は日本人補習校に通学した。1年もしないうちに忘れたかに見えていた英語を流暢に操り現地の友人とよく遊ぶようになった。現地校の優秀賞もしばしば獲得するようになる一方、週末の日本人学校も楽しみ日本の遊びもしばしばした。15歳時に高校受験に合わせて親たちより早く祖父母のもとに帰国した。高校入学後は時に日本語に不自由があるために授業についていくのが大変だとこぼす事はあったがそのたびにみずから英語のアドバンテージがあるからねなどと笑っていた。日米の長所欠点、経済問題について祖父と話すなど年齢に比し成熟していた。1学期の成績発表後期待以下だったと夏休みには日本語の遅れを取り戻すために予備校に通うなど熱心に勉強していた。2学期に入ると祖母に眠れないとこぼすようになり死にたいと言ったため受診となった。
うつ病の診断により薬物療法を開始し寛解した。本症例は日米両国への適応は良好で比較的成熟した適応であったが、過剰適応の内的破綻と共にうつ病を招来した症例である。
症例4 境界―同化型から追加保持型へ、診断名;パニック障害
18歳女子。3人同胞の第2子長女。満期安産初歩発語など発達上の問題は認めない。3歳時シンガポールへ。インターナショナルスクールに入学し小学校3年生まで滞在し、東京に戻り公立小学校に転入し私立中学入学。13歳時シンガポールに再び転地し元のインターナショナルスクールに転入した。インターナショナルスクールでは英語が母国語でないよく似た環境の子弟が多く友人は多く学校は楽しかった。17歳時に国際統一試験があり、それによって入学できる大学が決定するということもあり15歳頃からの勉強はもっぱらそれに向けてのものだった。首尾よく希望の名門校に帰国子女枠で推薦入学できた頃から不安発作がおこるようになった。親は1年に及ぶ単身の寮暮らしのためと考え卒業前であったがすでに兄の受験に合わせて帰国していた家族と合流させた。しかし、不安発作は改善せず医療機関への救急受診を繰り返すようになり受診となった。
本症例は2回、計7年あまり比較的日本人子弟の多いインターナショナルスクールで教育を受け学業成績も良く希望の大学に入学した同化型へ移行しつつあった境界型の症例である。インターナショナルスクールでの学習には基本的に不自由を感じないが日本での学習に比べると時間も努力も要すると患者は感じていた。家人からみると日本の進学校に通う兄より勉強や努力をしないように見えしばしば叱責していた。海外からの受験の方が有利とのことで海外の寮に単身生活した後合格した頃から「難しい大学でやっていけるだろうか」「日本の社会は厳しくはないだろうか」と不安発作が出現するようになった。再適応への不安が家人の患者への暗黙の評価を背景に出現した症例である。
おわりに
以上具体的な4症例を述べたが、 1. 子供たちは大人が考えるように「すぐ慣れる」は誤りである。子供たちの海外経験は、いわば大人がもっている海図もなしに海に投げ込まれる経験であり大人以上に困難を感じている。 2.「海外に居る」という事は「日本に居ない」という事で、海外体験が付加されるわけではなく、日本の不在の引き換え切符である。自動的に bilingualにはならない。 3. 言葉の分からない海外への適応は難しい。海外適応に苦労して疲れ果てた子供たちにとって日本への再適応はさらに心理的付加であり困難な事業である、ということを強調したい。周囲の大人たちが十分な配慮と理解をしていきたい。
[参考文献]
総務庁統計局編 日本の統計2000年 東京 2000
総務庁行政監察局編 いじめ・不登校問題などの現状と課題 東京 1999
総務庁青少年対策本部編 子供と家族に関する国際比較調査報告書 東京 1996
大阪医科大学卒業、日本医科大学精神医学教室講師を経て、コーネル大学医学部研究員。女性のうつ病、身体表現性障害の治療が専門。精神保健指定医、臨床心理士。日本サイコセラピー学会理事、日本臨床催眠学会理事、日本総合病院精神医学会評議員。