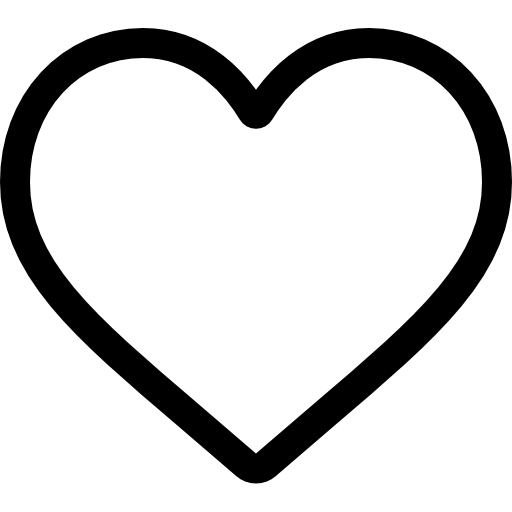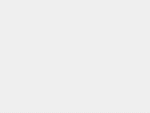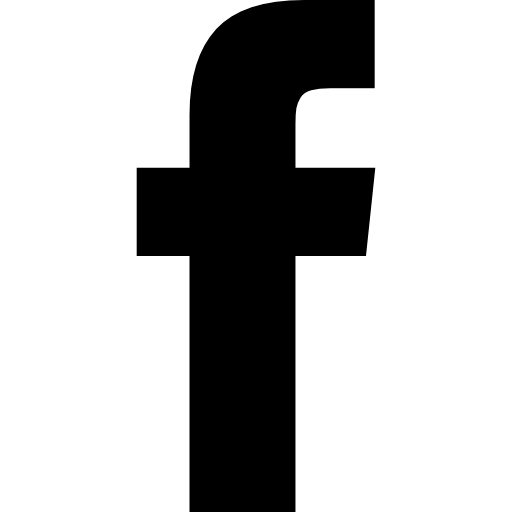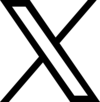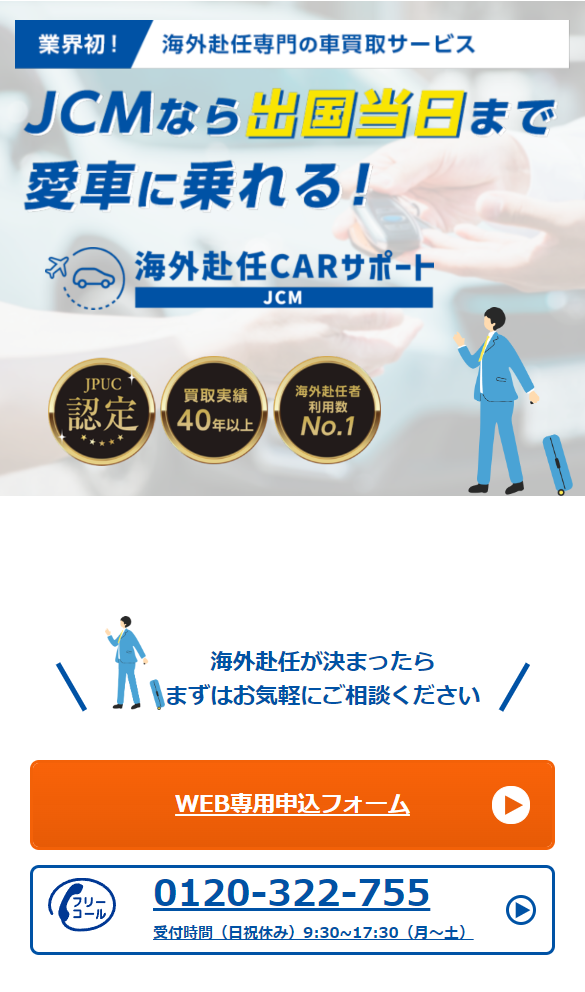赴任に必要な手続・届出
海外赴任中の納税や税金について
海外赴任中の納税や税金は、出発日や滞在期間、給与以外の所得の有無など、赴任者によって変わってきます。
しっかりと確認した上で、所定の手続きを行うようにしましょう。
 公開日:2024年7月31日
公開日:2024年7月31日
この記事で書かれていること
海外赴任中の所得税
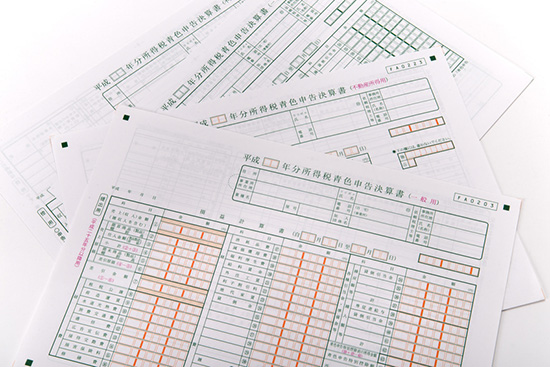
①赴任中の所得税は非課税
企業から派遣されて1年以上、海外へ転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
②赴任前の所得税の精算
海外赴任を開始した年の1月1日~出国日までに国内で得た給与に関しては、出国までに毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、控除などの手続きをします。注意点としましては、控除する保険料は、出国する日までに支払った金額を対象にして計算します。
また、配偶者控除や扶養控除は、出国時の現況で判断します。
配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
この調整による精算は非居住者となる時までに勤務先で行います。
③役員の例外
日本の法人の役員の場合には取扱いが異なります。その給与は、海外赴任中でも日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%の税率で源泉徴収されます。
この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約を結んでおり、租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先することになっています。
④給与以外の所得がある場合
一方、給与以外にも所得がある場合は詳細を確認しましょう。例えば、海外赴任中に自宅を賃貸して得た家賃収入や日本国内にある自宅などの不動産の売却収入は、課税対象です(国内源泉所得)。
この場合、出国前に納税管理人を決めて届け出ておきましょう。
年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して確定申告をします。
出国前に納税管理人を定めている場合は、納税管理人が翌年2月16日から3月15日までに本人に代わって確定申告を行います。
ちなみに、納税管理人とは、日本にいない納税者の代理で、確定申告や納税にかかる手続きを行います。
⑤赴任中に退職金をもらった場合
海外勤務中に退職金の支払いを受けた場合、原則として退職金を居住者期間分と非居住者期間分とに区分し、居住者期間分を国内源泉所得として20.42%源泉徴収されます。しかし、仮に全期間を居住者として退職金を受け取った場合と、またまた退職直前に非居住者として退職金を受け取った場合を比較すると税額に大きな差が生じることがあります。
このような場合に備えて、その退職金を全額居住者として受け取った場合の税額が、国内源泉所得のみについて非居住者課税を受けた場合の税額よりも少額である場合は、その差額を還付する制度があります。
国内勤務期間が長い赴任者が海外赴任中に退職するような場合には、居住者として退職金を受ける場合に比して、その支払い時の税負担が重くなる傾向がありますので、還付が受けられるかどうか検討しましょう。
この手続きとしましては、退職金の支払いを受けた年の翌年1月1日以後に、所轄の税務署に還付を受けるための確定申告書を提出する必要があります。
もし、退職後も引き続き、海外に居住している場合は、納税管理人を定めて、確定申告を行う必要があります。
⑥納税管理人の選任方法
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
詳細は勤務先の担当者に確認や、管轄の税務署に問い合わせましょう。
海外赴任中の住民税
①住民税の課税の基本
住民税は前年の1年間の所得を基に計算され、その年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。会社員である場合、毎月給与から差し引かれる方法(特別徴収)により6月~翌年5月にかけて、毎月納税することになります。
たとえば2017年4月に海外赴任した場合、2017年1月1日時点においては、日本に居住しているので、2018年6月から2019年5月分までの住民税は課税されます。
2019年分は2018年1月1日の時点で海外居住となっているため、課税されません。
②住民税の納付方法
(イ)会社で住民税の納付が全額納付あるいは継続する場合
国外へ転出する場合、残りの住民税を最後の給与から全額差し引く方法(一括徴収)や、出国後もその年の6月から翌年の5月までの住民税が会社の給与から差し引かれる場合(特別徴収)は、特に必要な手続きはありません。(ロ)普通徴収への切り替えをする場合
国外へ転出後、一括徴収を選択せず、残りの住民税を自分で納付する方法(普通徴収)を選択した場合、残りの住民税分の納税通知書が納税義務者本人に送付されます。その場合、納税通知書を受け取り、代わりに納税する納税管理人の選任が必要となります。
(ハ)納税通知書発送前の出国
出国した年の前年の所得に対する住民税の納税通知書は出国した年の6月初旬ごろに送付されます。翌年の住民税が課税される方(主に1月2日から6月中に出国された方)は、勤務先で特別徴収されない場合は、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年の住民税のための納税管理人の選任が必要となりますので、ご注意ください。
③納税管理人の選任方法
納税管理人を定めたときには、その非居住者の住所地の市区町村に「納税管理人の申告書」(自治体によって名称が異なります)を提出する必要があります。この申告書を提出した以後、市区町村が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、納税は非居住者の住所地の市区町村に対して行います。
住民税は地方税ですので、管轄の市区町村に詳細を確認しましょう。
また、勤務先による特別徴収の場合は、勤務先で手続きを行っています。担当者に詳細を確認しましょう。
海外赴任中の固定資産税・都市計画税
①固定資産税・都市計画税とは
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点において、日本国内に固定資産(土地、家屋等)を所有している場合に課税されます。なお、自治体によっては都市計画税がない場合もあります。
②納税管理人の選任方法
海外赴任中も固定資産税・都市計画税は課税されます。海外赴任中は、市区町村から送付される納税通知書の受領を含む納税に関する一切の事項を納税管理人が行うことになります。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の住所地の市区町村に「納税管理人の申告書」(自治体によって名称が異なります)を提出する必要があります。
この申告書を提出した以後、市区町村が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、納税は非居住者の住所地の市区町村に対して行います。
必要な場合は、出国前に納税管理人の選任をしておきましょう。
地方税ですので、管轄の市区町村に詳細を確認しましょう。
海外赴任中の事業税
①事業税とは
日本国内で家賃収入などがあり、事業税の課税対象者である場合、海外赴任中も事業税が課税されます。給料のみの会社員の場合は関係ありません。
②納税管理人の選任方法
海外赴任中も事業税の対象となる所得がある場合、事業税は課税されます。海外赴任中は、市区町村から送付される納税通知書の受領を含む納税に関する一切の事項を納税管理人が行うことになります。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の住所地の市区町村に「納税管理人の申告書」(自治体によって名称が異なります)を提出する必要があります。
この申告書を提出した以後、市区町村が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、納税は非居住者の住所地の市区町村に対して行います。
必要な場合は、出国前に納税管理人の選任をしておきましょう。
地方税ですので、管轄の市区町村に詳細を確認しましょう。
海外赴任時の税金に関するQ&A
- Q1.非居住とは何ですか?
- 非居住者とは、国内に1年以上住所も居所も有しない人をいいます。
1年以上海外の支店等に勤務するため出国したような人は、非居住者になります。
なお、国家公務員や地方公務員は、実際に国内に住所を有しない期間があっても、国内に住所を有するものとみなされます。
- Q2.単身で2年の予定で海外赴任します。給料の一部を日本の留守宅に支払うことになります。この場合、留守宅に支払う給料は日本で申告が必要でしょうか?
- 非居住者が受ける給料等については、日本国内において行う勤務に基づくものが国内源泉所得となり、日本の所得税が課税されます。
しかし、お尋ねの留守宅への給料は、たとえ日本国内で支払われたとしても、海外勤務に基づく給料ですので、日本では課税対象とはなりません。
日本での申告の必要はありません。
- Q3.当初3年の予定で海外赴任となり、海外赴任中の給料については日本の所得税は課税されていませんが、健康上の理由で6か月を過ぎたころ、帰国しました。この場合、海外赴任が1年未満となったので、赴任中に受けた給料は日本で課税し直すことになるのでしょうか?
- その必要はありません。
当初3年の予定で、海外赴任していますので、出国の翌日から非居住者としての扱いとなっています。
諸事情により、1年未満で帰国したとしても、海外赴任中は非居住者として、また、帰国後は居住者としての扱いになります。
- Q4.非居住者でも日本で確定申告しないといけない場合がありますか?
- 非居住者であっても、国内源泉所得(例えば、国内の自宅などの家賃収入や国内の不動産の譲渡など)がある場合は、納税管理人を定めて、確定申告を行う必要があります。
- Q5.納税管理人を定める場合は、いつまで行う必要がありますか?
- 国内で確定申告等が必要になる場合は、出国前までに納税管理人を定めておく必要があります。
出国後でもできないことはありませんが、手続きが煩雑になります。
海外赴任時の税金に関するまとめ
①赴任前に勤務先で所得税の精算をしましょう
②給与以外の所得がある場合(赴任中に自宅を貸すなど)、赴任中の納税の必要手続を確認しましょう
③住民税は1月1日時点において国内に住所がある場合に課税されます。出国の翌年にも注意しましょう
④固定資産税など地方税も確認しましょう
⑤納税管理人が必要な場合は出国前に手続きしましょう
※記事監修:大手町会計事務所(代表:大黒崇徳)
TEL:03-3518-9945
※お電話の際には「海外赴任ガイドを見た」とお伝えください
HP:http://tstyle-jp.com/