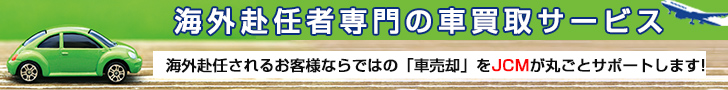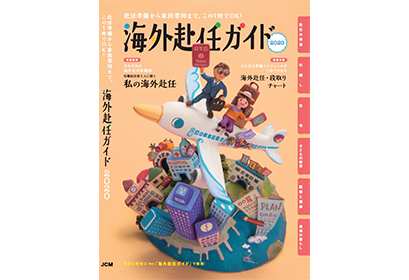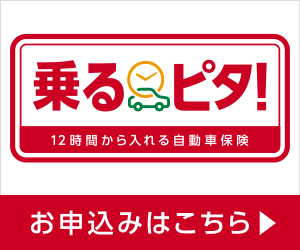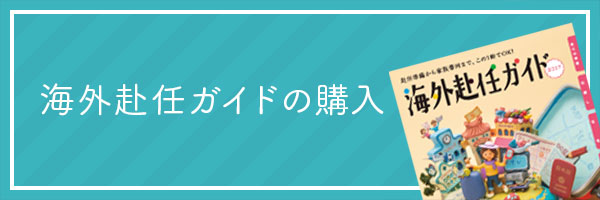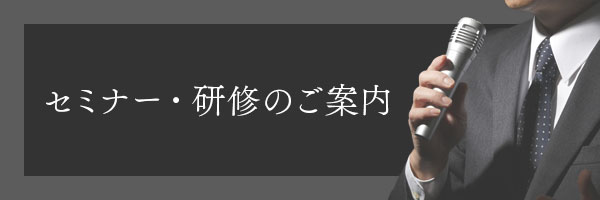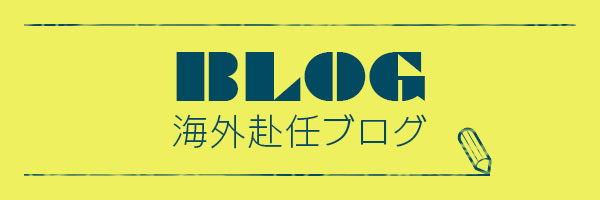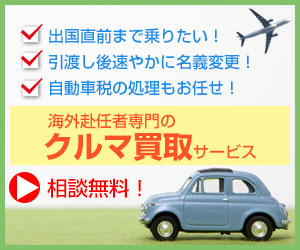26日(木)快晴。民主党の小澤一郎氏が代表選に出馬を表明した。まさかと思ったが、彼にふさわしいと言えばいえる。これで民主党は分裂に向かうということだろう。日本の政治家はもっと歴史観とか、思想信条で固まった方がいい。余りに利権がらみ集団だから。
26日(木)快晴。民主党の小澤一郎氏が代表選に出馬を表明した。まさかと思ったが、彼にふさわしいと言えばいえる。これで民主党は分裂に向かうということだろう。日本の政治家はもっと歴史観とか、思想信条で固まった方がいい。余りに利権がらみ集団だから。
フィンランドの状況をもっと詳しく報告する気になった。フィンランドには教師評価がない。なぜなら、この国では教師は、弁護士、医者と同じように、専門家とみなされ、職業的地位が高く、教養があり尊敬されている。教師になるのは厳しいが。
教員養成のシステムでは戦後むしろ日本が先行していたが、フィンランドでは68年になってからである。教員養成学科が大学に併設され、5年間の在学期間のうちほぼ半年間は教育実習に当てられる。(ドイツはもっと長い2年間のインターン制度だ)
 修士課程修了を教師資格の必修条件としたのは79年になってからである。91年には視学(学校査察)制度が廃止された。日本で言う管理主事や指導主事のことで日本ではむしろ増やし、無駄な経費をかけて管理を強めているのだ。92年には教科書検定も廃止された。
修士課程修了を教師資格の必修条件としたのは79年になってからである。91年には視学(学校査察)制度が廃止された。日本で言う管理主事や指導主事のことで日本ではむしろ増やし、無駄な経費をかけて管理を強めているのだ。92年には教科書検定も廃止された。
これらの動きが不況の中で「小さな政府づくり」のために行われたというから面白い。ただ、単に経済効率のために教育を削ったのではない。教育再生のために、中央集権制度を見直し、地方分権、学校自治を推進するという理念に基づいているのである。
当時の教育相ヘイノネンの言葉「学ぶということは大変繊細で複雑な事柄です。私たちはそうした本来の教育を受けさせるために、多くの権限をそれぞれの現場、つまり生徒、教師そして校長に任せたのです。国が決して阻害してはならないのです」
 「というのも最も重要なのはモチベーションだからです。教師の意欲、生徒の学習意欲、それこそが核心なのです。厳しく管理すれば、モチベーションが失われ、結局何もかもがダメになってしまうのです」これがフィンランドの保守派で新自由主義者の言葉なのだ。
「というのも最も重要なのはモチベーションだからです。教師の意欲、生徒の学習意欲、それこそが核心なのです。厳しく管理すれば、モチベーションが失われ、結局何もかもがダメになってしまうのです」これがフィンランドの保守派で新自由主義者の言葉なのだ。
従って、国と地方自治体の行う教育評価は「国家カリキュラム」(日本の学習指導要領にあたるが、ガイドラインでいわば大綱である)が適切であったか、教育予算が正しく配分されたか、教育条件が十分であったかを評価するもので、教師を評価するものではない。
国家教育委員会(文科省)の一人レイヨ氏は「学校を評価する場合に、我々の目的は教職員に支援的であること、教職員の発達を助けることです。我々は案内を提示するだけであって、批判はしない。調査内容を公開したり良い学校とか悪い学校の一覧表も作らない」
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。