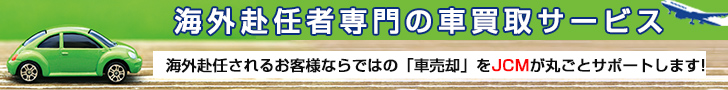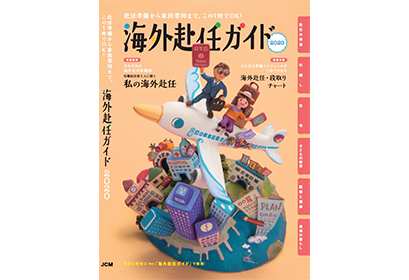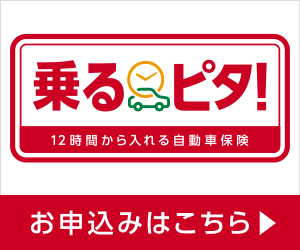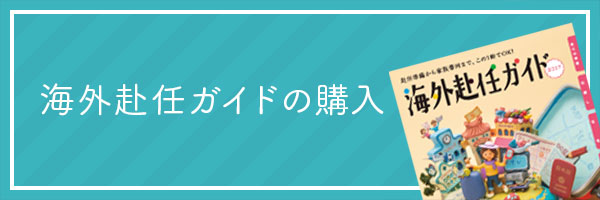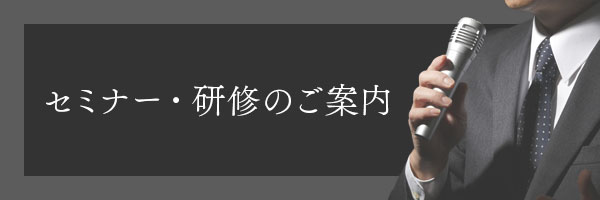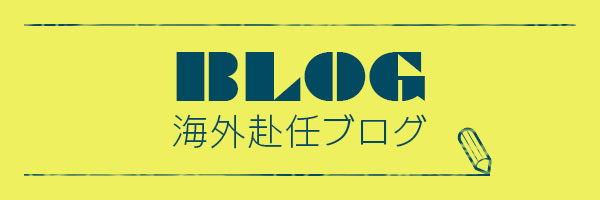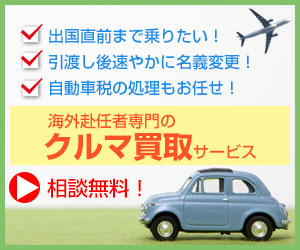25日(月)曇り時々雨。私の友人でバンコク在住のフリーライター藤岡和幸氏がいる。氏は私も会員であるNGOメコン基金創立に関わり、今も通訳兼で会の活動に関わっておられる。氏のブログをチェックするのが日課になっている。今はタイ東北部報告である。
25日(月)曇り時々雨。私の友人でバンコク在住のフリーライター藤岡和幸氏がいる。氏は私も会員であるNGOメコン基金創立に関わり、今も通訳兼で会の活動に関わっておられる。氏のブログをチェックするのが日課になっている。今はタイ東北部報告である。
メコン基金の活動はラオスやタイの学校建設活動や里親を通して中高校生に奨学金を援助する活動が中心になっている。今年度は165名の(中103名、高62名)子どもたちに贈られている。今会の代表に同行してラオス、タイ東北部を回られているのだ。
私が半年間お世話になったタイの学校の校長がブログに登場しており、懐かしくなった。ノンカイ県の教育長になったらしい。今思い出すと、日本語教育に熱心で、個性豊かな校長だった。タイの校長の権限が強く、校長の個性がもろに学校運営に反映する。
 例えば校庭を農機具の展示会場に貸し出して料金をとったり、校庭の木を伐採して売る、スポーツや文化的な催しを校内でやる時も出店から場所代をとって収入にする。日本ではそもそもそんなことは非常識となるだろうし教委の許可が必要となるだろう。
例えば校庭を農機具の展示会場に貸し出して料金をとったり、校庭の木を伐採して売る、スポーツや文化的な催しを校内でやる時も出店から場所代をとって収入にする。日本ではそもそもそんなことは非常識となるだろうし教委の許可が必要となるだろう。
校長は学校予算の金策のために出張が多く、ほとんど学校にいなかった。(これは欧米でも同様で、一般教員の出張はほとんどない)だから学校の重要事項を決定する会議は校長がいるとき、授業を切り上げて行い、5時にはきっちり終わるのが普通だ。
この校長は学校にいる時は生徒指導の先頭に立つ。容赦なく生徒を怒鳴りつけ、親を呼びつける。職員に来た親からの苦情にもピシャリとはねつけ、職員を守る。それは感心したのだが、先生方に自分の考えを徹底しないから、校長がいないときはだらける。
 となり村の中規模校の学校の校長はタイプの違う、穏やかな人だったが、その下にいた女教頭が素晴らしい人物で職員も生徒もきちんとし、校舎も常に整理整頓されていた。大綱的なカリキュラムはあるらしかったが、基本的には学校の方針に任されていた。
となり村の中規模校の学校の校長はタイプの違う、穏やかな人だったが、その下にいた女教頭が素晴らしい人物で職員も生徒もきちんとし、校舎も常に整理整頓されていた。大綱的なカリキュラムはあるらしかったが、基本的には学校の方針に任されていた。
この女教頭は優秀な人でバンコクにも招聘されたのを断り、自らへき地教育と恵まれない子どもたちの世話に打ち込んでいた。日本語を自由に話したのでタイの教育について突っ込んだお話を伺えた。彼女を慕ってへき地教育に飛び込んできた若い教師もいた。
日本の学校が画一的なのは学習指導要領のせいであり、文科省―教委―校長という上意下達の仕組みであり、校長や一般教員に判断をさせない徹底した管理教育のせいである。街頭でマイクを向けられると、周囲を見渡し、自分の意見を言えないのが日本の若者だ。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。