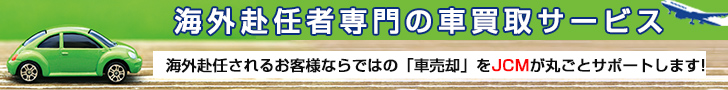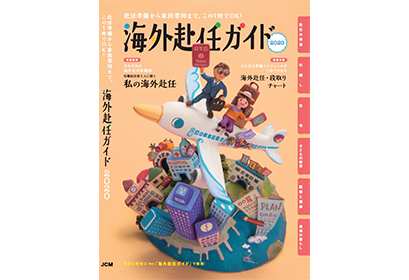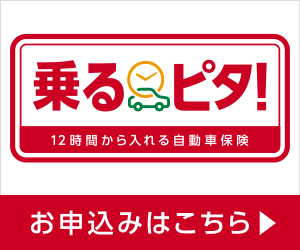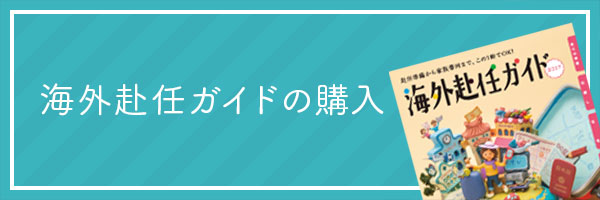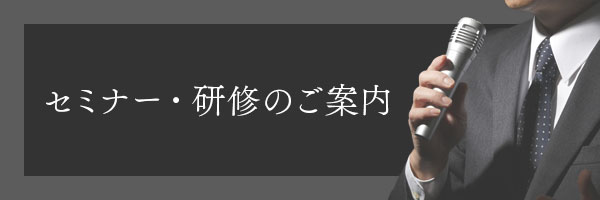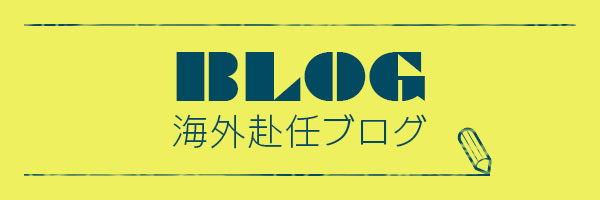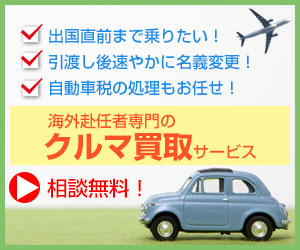23日(土)快晴。佐渡汽船近くにできた魚、肉、野菜等の総合マーケットが開店したというので行ってみた。土曜日とあってかなりの賑わいだったが、あっと驚くほどの安さはなかった。特に野菜はむしろ高い程で少々がっかり。でも今までなかったのが不思議だ。
23日(土)快晴。佐渡汽船近くにできた魚、肉、野菜等の総合マーケットが開店したというので行ってみた。土曜日とあってかなりの賑わいだったが、あっと驚くほどの安さはなかった。特に野菜はむしろ高い程で少々がっかり。でも今までなかったのが不思議だ。
教員が多すぎ、恵まれ過ぎているという、小泉政権時代の「経済財政諮問会議」の報告に声を大にして反論しておきたい。05年頃の報告に「子どもの数が減っているのに先生の数が増えることはあり得ない」「この間、先生の数を増やしても学力は低下したではないか」
という粗雑極まりない意見である。日本の教育予算は国際的に水準が低く、教職員の数も諸外国に比べ随分と低い。例えば予算では1位のアイスランド、ニュージーランド、スイス…12位に韓国、メキシコと続き、日本はOECD加盟国中、下から5位である。
 教員数も教員一人当たり生徒数は就学前18人、初等19.9、前期中等15.7、後期中等13.5人で、いずれもOECD各国平均(14.4、16.5,14.3,13)を上回っている。学力世界一のフィンランドに比べ教員配置は小60%、中65%である。なによりも自主性、自由がない。
教員数も教員一人当たり生徒数は就学前18人、初等19.9、前期中等15.7、後期中等13.5人で、いずれもOECD各国平均(14.4、16.5,14.3,13)を上回っている。学力世界一のフィンランドに比べ教員配置は小60%、中65%である。なによりも自主性、自由がない。
少子化により欧米並みの少人数学級、無免許運転廃止、図書館司書、学校カウンセラーの全校配置のチャンスなのに、やっと40人学級の法制化、35人学級の実現が言われるほどに立ち遅れているのだ。政府の諮問会議で「多すぎる」議論が出ること自体恥ずかしい。
どれほど恥ずかしいか。ユネスコは1966年に「教員の地位に関する勧告」を採択しているが、「教育の発展における教員の本質的役割」を重視し、教員の教育の専門職にふさわしい教員の地位に関する諸原則」(後日詳述)が盛り込まれているが日本の違反は明白。
 学級の規模に関して言えば、86項に「学級の規模は、教員が個々の生徒に注意を向けることができる程度のものとする」とあり、欧米諸国では20~30人が大勢となっている。このユネスコ勧告は条約ではないことをいいことに、日本政府はサボり続けてきたのだ。
学級の規模に関して言えば、86項に「学級の規模は、教員が個々の生徒に注意を向けることができる程度のものとする」とあり、欧米諸国では20~30人が大勢となっている。このユネスコ勧告は条約ではないことをいいことに、日本政府はサボり続けてきたのだ。
さらに教員攻撃は給与が高すぎることに及んで、例の人材確保法案によってできた教職調整手当4%の削減に手をつけようとしている。財務省は根拠もなく11%高いと宣伝している。教員に残業手当が支給されないことを無視し、基本給だけで比較している。
家に持ち帰らざるを得ない仕事(教材づくり、テスト問題の作成、採点等々)平日の放課後や土日もない部活動の指導、荒れた学校では深夜に及ぶ生徒の指導、家庭訪問、会議など残業手当のでないサービス残業である。それこそ民間ではあり得まい。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。