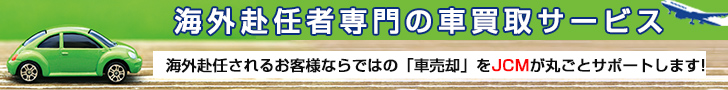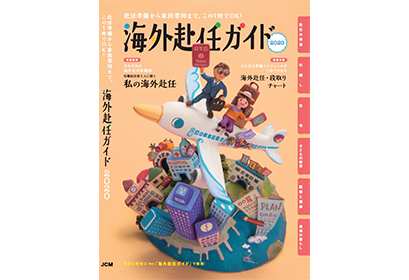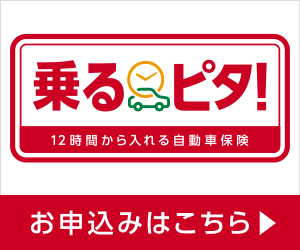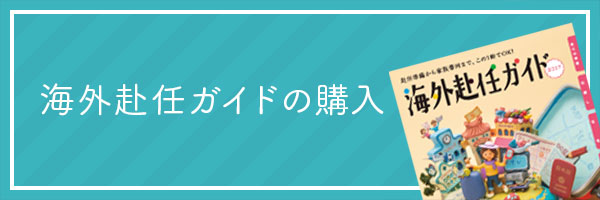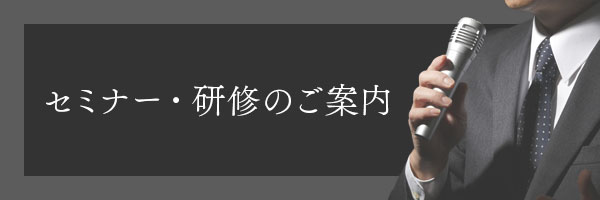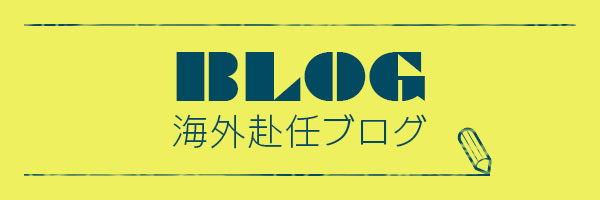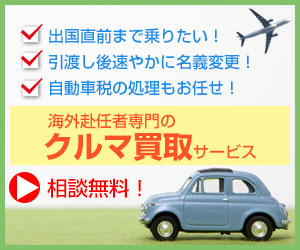31日(火)快晴。9月を迎えるというのに日中は30度を下回ることがない。ほんとにこれでは家にいるしか方法がない。山小屋は涼しかったなあ。尾瀬ヶ原は標高1400。小屋の朝は早いから夕食も早く5時半である。消灯が9時だからたっぷり快適な時間がある。
31日(火)快晴。9月を迎えるというのに日中は30度を下回ることがない。ほんとにこれでは家にいるしか方法がない。山小屋は涼しかったなあ。尾瀬ヶ原は標高1400。小屋の朝は早いから夕食も早く5時半である。消灯が9時だからたっぷり快適な時間がある。
福田誠治著「フィンランドは教師の育て方がすごい」をかなり読み進んだ。このシリーズも長くなりそうである。日本の教育を何とかしなければ将来がないように思われる。この本を読んでいると、フィンランドも70年頃までは今の日本と同じ状況だったと。
 フィンランドはスエーデンとドイツに学びながら、改革を試行した。どこの国に学ぼうとも構わない。先ずは日本のどこがおかしいのかに日本人の多くが気付かないことには改革は始まらない。前回紹介した「みんな同じである必要はない」は重要な指摘ではないか。
フィンランドはスエーデンとドイツに学びながら、改革を試行した。どこの国に学ぼうとも構わない。先ずは日本のどこがおかしいのかに日本人の多くが気付かないことには改革は始まらない。前回紹介した「みんな同じである必要はない」は重要な指摘ではないか。
日本の学校は(職場も)「みんなが同じであること」を求める教育だ。口では個性の尊重を言いながら、やっていることは逆だ。学級、学年、全校単位で子どもたちを動かす。そのために教師もその単位で企画・運営にあたる。それが「まとまり」だと。
70年代以降40年に及ぶ教育改革は粘り強く時間をかけて行われてきた。その一つに「授業だけでなく、カウンセリング、健康、食事、特別なニーズの教育等においても公費負担を受けてすべての子どもに同じ最高の質を提供する」徹底した平等主義の考え方がある。
 日本では平等というと、「全く同じこと」を意味する。極端に言うなら、同じクラスなら同じ日に同じことを教えてもらうことが平等だと。これを突き詰めれば、教科書も同じ教科書で教えて欲しい、テストも同じテストで一斉に受けさせて欲しいとなる。
日本では平等というと、「全く同じこと」を意味する。極端に言うなら、同じクラスなら同じ日に同じことを教えてもらうことが平等だと。これを突き詰めれば、教科書も同じ教科書で教えて欲しい、テストも同じテストで一斉に受けさせて欲しいとなる。
全国一斉学力テストを抽出で受けなくてもいいと言ってもそれでは不平等だと考える親が多いということだ。保守系の政治家が習熟度別学習を主張し、競争を奨励し、学校選択性を主張するのもフィンランド式の考え方で言えば両方とも間違いだということになる。
 「平等は誰にも同じものを提供するのではなく、誰もが自分の才能にあった教育を入手する権利である」これは新自由主義に基づく考え方で、一見もっともに聞こえる。ところがフィンランドがとった政策は「家庭環境によって能力発達が押しとどめられることがないように、環境格差を社会が埋めていくことになる。条件の悪い者にこそ手厚く支援をするというわけだ。教育はできない人の底上げはするが、できる人は放っておくんです」これには説明が必要だが、とにかくフィンランドでは学校格差、地域格差がないような政策実現によって、学校選択の必要もなく、無意味な状況が作り出されているというわけだ。
「平等は誰にも同じものを提供するのではなく、誰もが自分の才能にあった教育を入手する権利である」これは新自由主義に基づく考え方で、一見もっともに聞こえる。ところがフィンランドがとった政策は「家庭環境によって能力発達が押しとどめられることがないように、環境格差を社会が埋めていくことになる。条件の悪い者にこそ手厚く支援をするというわけだ。教育はできない人の底上げはするが、できる人は放っておくんです」これには説明が必要だが、とにかくフィンランドでは学校格差、地域格差がないような政策実現によって、学校選択の必要もなく、無意味な状況が作り出されているというわけだ。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。