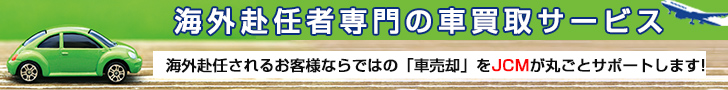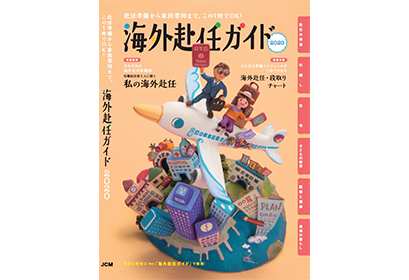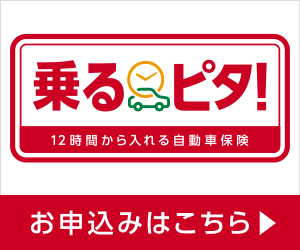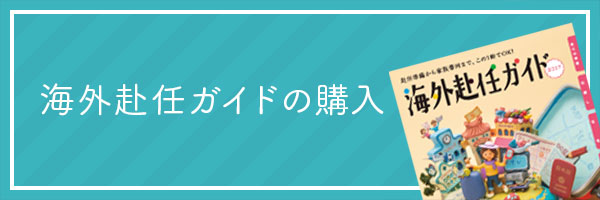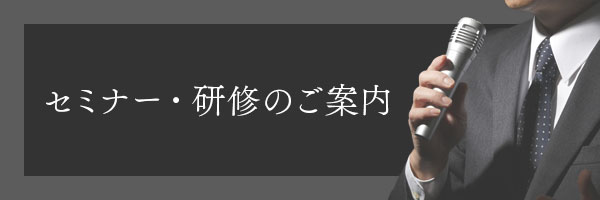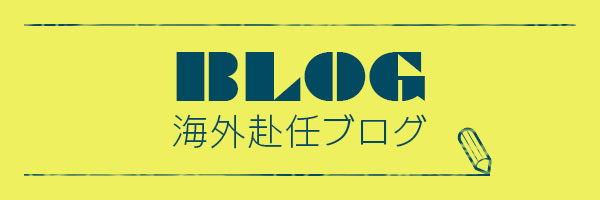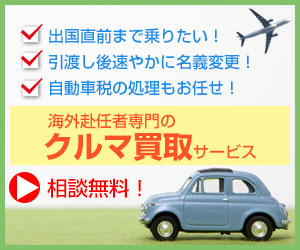4日(土)快晴。今日はいくらか風もあり、しのぎやすい日だった。さて今市内何カ所かで学校統合が問題になっている。大体日本の学校統合というのは、経済効率以外の話で聞いたことがない。フィンランドでは小規模校を政策的に残し、大切にする。その実態。
4日(土)快晴。今日はいくらか風もあり、しのぎやすい日だった。さて今市内何カ所かで学校統合が問題になっている。大体日本の学校統合というのは、経済効率以外の話で聞いたことがない。フィンランドでは小規模校を政策的に残し、大切にする。その実態。
個々人に合ったきめ細やかな教育の実現という観点で議論が行われた。その結果、地域の小規模校の方が、柔軟な時間割が組め、個人指導ができ、生徒たちによる自律的活動や野外授業が可能で、為すことで学ぶという教育方法が実現される。さらに地域と学校との緊密な連携ができるという合意に至った。ここには徹底して子ども中心主義が見える。
言われてみれば、自分の37年間の教員生活を振り返ってみて新卒から200人規模の小規模校が4校、シンガポールは400人の中規模、1000人規模の大規模校が2校だった。生徒、親、地域との緊密さ、授業のやり易さ、あらゆる面で小規模校の方が優れていた。
 大規模校で盛り上がるのは日本的な運動会くらいではないか。80年代の学校の荒れは統廃合の進んだ結果も一つの原因ではなかったかと、こじつけたくなる。フィンランドでは本格的な教育改革が始まった94年段階で、腹式学校が半数を占めていたという。
大規模校で盛り上がるのは日本的な運動会くらいではないか。80年代の学校の荒れは統廃合の進んだ結果も一つの原因ではなかったかと、こじつけたくなる。フィンランドでは本格的な教育改革が始まった94年段階で、腹式学校が半数を占めていたという。
先の合意に基づいてヘイノネン教育相の音頭とリで政府のとった方式は、どの地域でも学べるように学校にコンピューターを普及させ、それを高速通信LANでつなぐことだった。例えば、人口5500人にある、住民200人のスヴィラ小学校である。
学校が唯一の文化施設である。(日本の山間部も状況は同じだろう)学校は子どもの授業のほかに、大人のクラブや集会に使われていた。地域からは野外スポーツ施設、校外学習やキャンプ、専門家を学校へ派遣するなどの支援を受けていた。
生徒数は27人、教師は2人(内一人は校長だが、当然授業を担当)英語教師、特別支援教師、養護教師は複数校掛け持ちで巡回してくる。問題があれば臨時に教師が加わり、用務員(給食、掃除、その他の世話)、教師は1~2年担任と3~6年担任。
 フィンランドの凄いところは、当時新自由主義が欧州にも吹き荒れたのだが、企業化連合が国家標準に基く中央集権的な学校管理を提案したのに政府はそれをはねのけ、全く逆の政策、つまり、国家カリキュラムをガイドラインに転換し、中間管理職を縮小し、現場を厚くする。詰め込み、競争を一切排除し、子どもが自ら学ぶ、しかも協同で学ぶような学習を組織することとした。従って教師の評価は比べられないとの観点に立って教員評価も廃止された。新自由主義の原則を都合よく取り込んだというわけだ。
フィンランドの凄いところは、当時新自由主義が欧州にも吹き荒れたのだが、企業化連合が国家標準に基く中央集権的な学校管理を提案したのに政府はそれをはねのけ、全く逆の政策、つまり、国家カリキュラムをガイドラインに転換し、中間管理職を縮小し、現場を厚くする。詰め込み、競争を一切排除し、子どもが自ら学ぶ、しかも協同で学ぶような学習を組織することとした。従って教師の評価は比べられないとの観点に立って教員評価も廃止された。新自由主義の原則を都合よく取り込んだというわけだ。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。