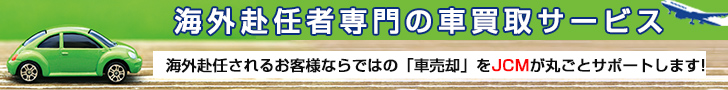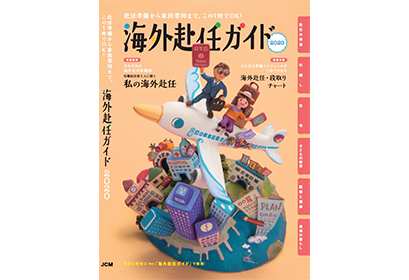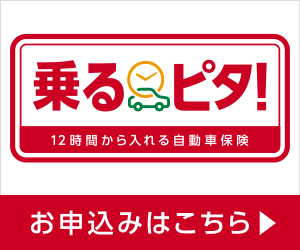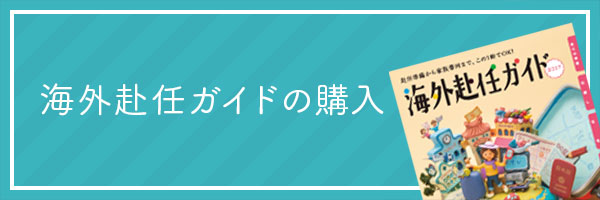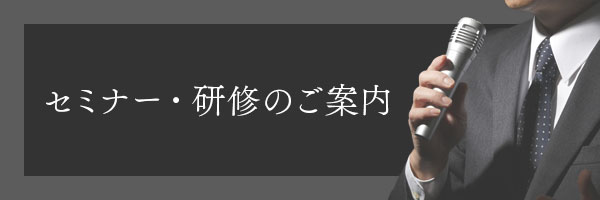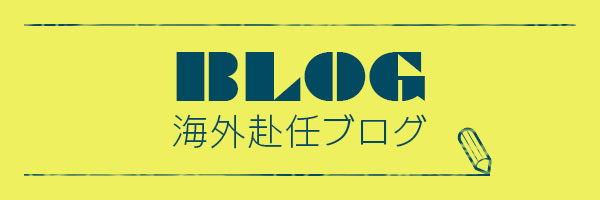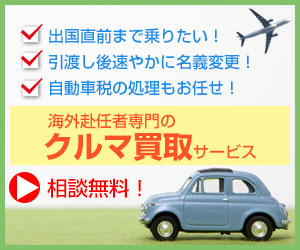29日(日)夕方5時半になっても32度もある。以前よりもっと暑い感じだ。最近山小屋が高いのは下界並みの設備を整えるからだ。果たしてそんな必要があるのだろうか。石鹸やシャンプー、バイオトイレを設備しながら、自販機を設置するなど矛盾している。
29日(日)夕方5時半になっても32度もある。以前よりもっと暑い感じだ。最近山小屋が高いのは下界並みの設備を整えるからだ。果たしてそんな必要があるのだろうか。石鹸やシャンプー、バイオトイレを設備しながら、自販機を設置するなど矛盾している。
山の中は不便なものだ、下界で手に入るものも入らないところだと思わせるのも環境行政ではないのか。尾瀬と言えば、初めて尾瀬に山小屋を開業した長蔵小屋の平野長蔵親子の尾瀬に通ずる道路建設阻止の運動が日本の環境運動の原点ともいえるものだった。
 あの親子の運動がなければ、今頃尾瀬沼や尾瀬ケ原まで車で入り込めるようになって、湿原は失われた可能性が高い。それも孫の代になって宿泊客が残していったゴミを周辺に埋め立てて、土壌を汚染したことが発覚した事件があった。設備充実に伴う必然だった。
あの親子の運動がなければ、今頃尾瀬沼や尾瀬ケ原まで車で入り込めるようになって、湿原は失われた可能性が高い。それも孫の代になって宿泊客が残していったゴミを周辺に埋め立てて、土壌を汚染したことが発覚した事件があった。設備充実に伴う必然だった。
ついNZの環境行政と比較してしまうのだが、山の鼻ビジターセンターには制服を着た学芸員のような人が何人かいて来客への解説や案内をしていた。おそらくこの季節だけだろう。今回に限らず尾瀬を歩いていて外で作業をしている彼らに会ったことがない。
 NZではビジターセンターの様子は同じだが、彼らとは別にパークレンジャーと呼ばれる森や登山道を整備したり、アンマナーな登山客に注意や指導、案内をしたり、トイレの掃除、紙の補充をして巡回している人たちに必ず出会う。若い人が多かった。
NZではビジターセンターの様子は同じだが、彼らとは別にパークレンジャーと呼ばれる森や登山道を整備したり、アンマナーな登山客に注意や指導、案内をしたり、トイレの掃除、紙の補充をして巡回している人たちに必ず出会う。若い人が多かった。
尾瀬は国立公園だ。レンジャー隊員の存在ばかりではなく、翌朝平滑(ひらなめ)の滝1.7キロの木道は朽ちて危険な個所さえあった。熊の生息地で熊に出会ったときの注意事項や熊よけの鐘が設備してあっても、いざというときの備えがない。予算がないのだろう。
 尾瀬は水資源の宝庫であり、群馬、福島、新潟の3県がその水利権を争ってきた。そこに東京電力などの電力会社の利権がからみ、一時は至仏山の中腹にダムを建設する計画さえあった。近年電力会社は世論に気を使い環境保全のための経費を負担するようになった。
尾瀬は水資源の宝庫であり、群馬、福島、新潟の3県がその水利権を争ってきた。そこに東京電力などの電力会社の利権がからみ、一時は至仏山の中腹にダムを建設する計画さえあった。近年電力会社は世論に気を使い環境保全のための経費を負担するようになった。
その金額やその負担程度が妥当なものなのかどうか、私は調べていないが、日本の環境行政全般が企業寄りである現実を思えばとても十分なものではないことは予測がつく。水資源を守るためなら、木道整備やパークレンジャーの経費の負担を求めるべきではないか。
日本の滝は東南アジアやNZの滝に比べてもやはり、格段に美しい。特にこの平滑の滝は落ちる滝ではなく巨大な岩盤の上を川のごとく流れるさまは最初圧倒された。今回懐かしくて再び訪れた。今回の尾瀬の旅で覚えたトリカブトやヒツジ草も美しかった。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。