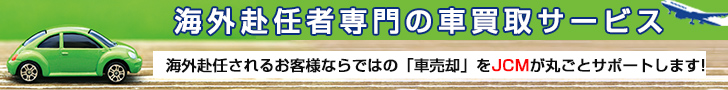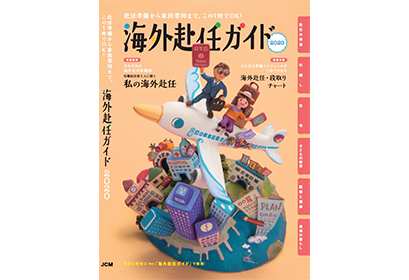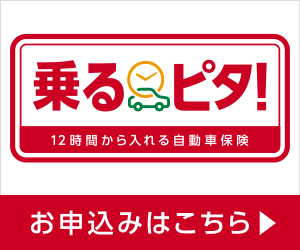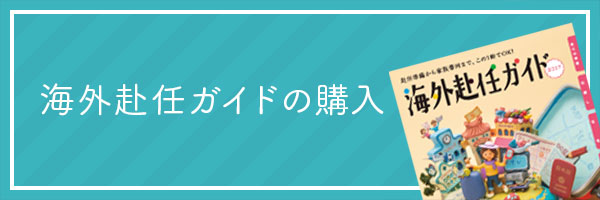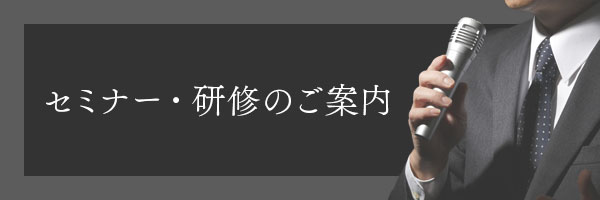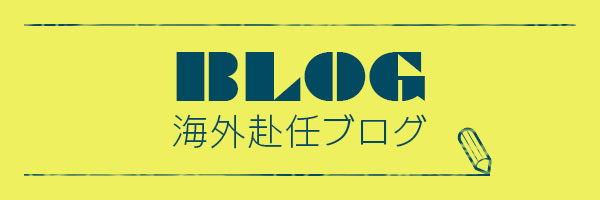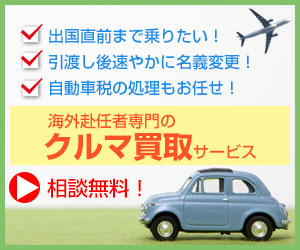24日(火)快晴。全国同じ傾向だろうが、新潟の高校ではすでに学校が始まっている。夏冬等長期休暇は限りなく短縮され、授業も7限を設定する学校が広がっている。理由はすべて学力向上のための授業時数の確保であり、競争に勝ち抜くためである。
24日(火)快晴。全国同じ傾向だろうが、新潟の高校ではすでに学校が始まっている。夏冬等長期休暇は限りなく短縮され、授業も7限を設定する学校が広がっている。理由はすべて学力向上のための授業時数の確保であり、競争に勝ち抜くためである。
ただ競争を煽るだけの学力テストが今年も4月に実施された。文科省は3割の抽出としたにも拘わらず、全校参加が秋田、福井など13県、本県は70%以上の学校が参加したという。理念に基づく参加ではなく、世間の批判を恐れての消極的参加であることは明らかだ。
対象が小六と中三だと言うだけでも、文科省がいう「子どもの学力の追跡調査が不可能」であることは明白である。結果は1位から47位までランク付けされ、「一点でも多く」と親は子どもの、教委は学校の尻を叩く点取り競争になるのは目に見えている。
 先日の日報社説でも「横並び出なければ安心できず、しかも結果に一喜一憂する。地方の教育行政のそんな姿が見え隠れしている。自分たちが行っている教育に対する自信の無さを表したものと言っていい」と批判している。全く同感である。
先日の日報社説でも「横並び出なければ安心できず、しかも結果に一喜一憂する。地方の教育行政のそんな姿が見え隠れしている。自分たちが行っている教育に対する自信の無さを表したものと言っていい」と批判している。全く同感である。
今の読書は朝鮮関係と教育問題に関わるものばかりだ。再びフィンランドの本を見つけて県立図書館から借りてきた。日本の教師の労働条件の異常さが浮かび上がってくる。07年の国民文化総合研究所の調査で日、英、スコットランド、フィンランドの比較である。その内容を紹介していく。
あるフィンの教師は朝7時34分に家を出て、7時56分に学校着。授業開始は8時16分、日本と変わらない。ところが授業終了時刻は14時9分で学校を出る時刻は14時57分。帰宅は15時29分。彼らの在学校時間は7時間1分。日本は11時間26分(平均)である。
 フィンランドに限らず、欧米及び東南アジアでも教師の義務は授業時間のみであり、その他は自己研修時間とみなされる。その研修は学校でも、図書館でも、どこでやってもよいと社会的にみなされている。教師はそういうことのできる専門家とみなされている。
フィンランドに限らず、欧米及び東南アジアでも教師の義務は授業時間のみであり、その他は自己研修時間とみなされる。その研修は学校でも、図書館でも、どこでやってもよいと社会的にみなされている。教師はそういうことのできる専門家とみなされている。
日本の教師は夏休みも事実上なく、毎日出勤して無駄な会議と事務処理のために不毛な努力を強いられている。フィンでは「教育方針の作成、事務報告、教材の管理、その他の記録文書の作成」にかける時間は月1.1回、日本の教師は10.3回である。
フィンランドではほとんどの教師(7割、日本は7割近く事務処理)はペーパーワークをしていない。つまり、ノルマは授業だけであり、授業の運営は個々の教師に任されており、他の管理者に向かって文書を作成するようなことは不要だということである。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。