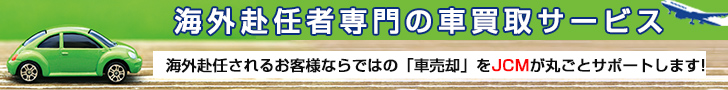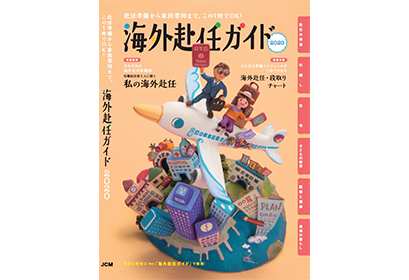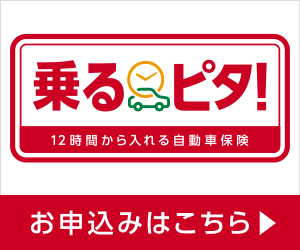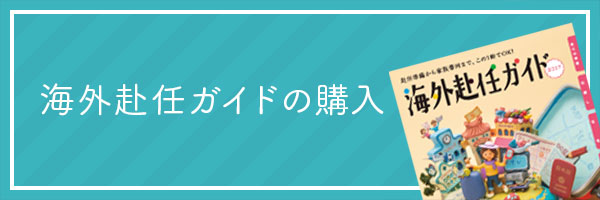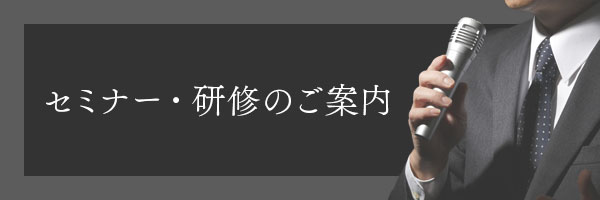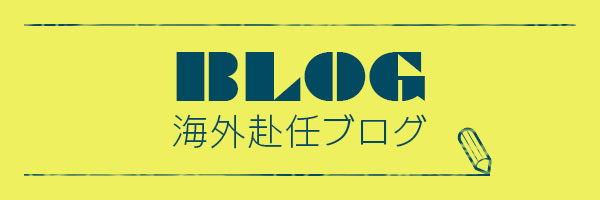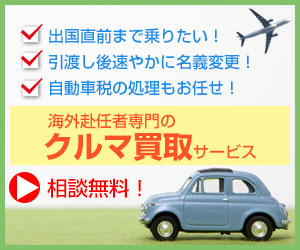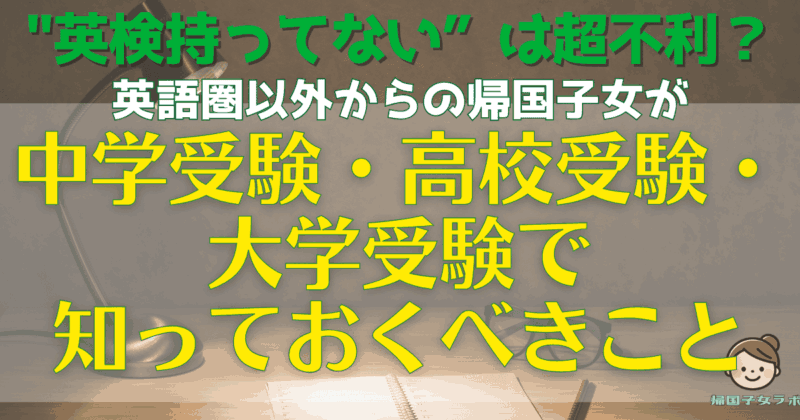
「英検を持っていないと、大学受験で不利になる」
——そんな声が現実味を帯びてきました。
2025年10月の報道(東洋経済オンライン:”英検未取得は超不利”令和に「取り残された」地方)によると、英語力を証明する資格の有無が、地方の受験生に大きな格差を生んでいるという指摘が出ています。
ここで気になるのが「非英語圏からの帰国子女」は英検をどのようにとらえているのか?ということです。
海外で育つ帰国子女の就学ルートは、日本人学校・現地校・インターナショナル校と多様です。
非英語圏でも、英語で学ぶインターに通って英語が日常になっている子がいる一方、日本人学校や現地語中心の学校に通い、英語に触れる時間が少ない子も少なくありません。
いずれのケースでも、日本の受験では英検やTOEFLなど“日本の基準での証明”が求められる場面が増えており、実力があっても資格が無ければ評価に結び付きにくいのが現実です。
だからこそ、環境に関わらず早めに資格取得の計画を持つことが重要になります。
この記事では、
文科省のデータから見える「英語力の地域差」 大学入試で英語資格が重視される理由 非英語圏からの帰国生が抱える課題と具体的な備えを、データと実体験の両面から整理します。
「非英語圏からの帰国でも、確実に評価される準備」を一緒に考えていきましょう。
文部科学省が公表した調査によると、全国の中学生のうち英検など外部試験を受験した生徒は約45.7%、CEFR A1レベル以上の英語力を持つとされる生徒は52.4%にとどまっています。
つまり、半数近くの生徒が「英語力を客観的に証明できていない」状態です。
特に地方では、英検受験率そのものが低く、英語力を“資格として可視化”できないまま受験を迎えるケースが多く見られます。
たとえば、秋田県の外部試験受験率は 91.9% と全国トップクラスですが、神奈川県は 30.1%、島根県は 23.9% と大きな差があります。
このように、英語力の「地域格差」 は確実に存在しています。
帰国子女の日本国内分布:東京が圧倒的に多いさらに、帰国子女の受け入れ状況を見ても、地域差は明確です。
多くの帰国子女は、教育環境や受け入れ校が整っている東京圏を中心に帰国しています。
特に東京都内では、以下の自治体が突出しています。
自治体直近5年間の帰国子女数年平均世田谷区1529人約306人/年杉並区575人約115人/年文京区565人約113人/年目黒区533人約107人/年港区434人約87人/年このように、東京23区の多くは帰国子女受け入れ実績があり、英語教育サポート体制も整備済み。
一方で地方では、受け入れ校の選択肢が限られ、英検などの外部資格が“評価の基準”としてより重要になります。
秋田県は、文科省の調査で常に上位に入る“英語力優等県”。
その背景には、教育体制そのものの強さがあります。
英検IBAの導入:秋田県では英検の代替として「英検IBA(英語力診断テスト)」を中高生に広く導入。これにより、英語力の客観的評価と学習意欲の向上を図っている。 自治体目標の設定:国の目標(CEFR A1以上50%)を超える県独自の目標値(60%)を掲げ、教育委員会が積極的に取り組んでいる。 学習環境の安定性:全国学力テストでも常に上位に位置する秋田県は、落ち着いた授業環境と丁寧な指導が定着しており、英語以外の教科でも高い成果を出している。 教員の意識と責任感:英語教育に限らず、教員が生徒の基礎学力向上に強い責任感を持って取り組んでいることが、全体的な学力底上げにつながっている。秋田では、英語を“受験科目”ではなく“地域全体の教養”として扱う空気があるんですね!
その結果、地方でも高い英語力を維持できているのです。
秋田大学も英語教育に力を入れており、英語による授業や留学支援制度が充実しているため、地域全体で英語力向上への意識が高いと考えられます。
大学入試で「英語資格」が重視される理由ここ数年、大学入試では英語4技能(読む・書く・聞く・話す)を総合的に評価する動きが急速に広がっています。
特に英検・TOEFL・IELTSなどの外部試験スコアが「出願要件」や「加点対象」として扱われるケースが増加中。
文部科学省の調査では、全国の大学の約63%が英語資格を何らかの形で入試に活用しており、
その内容も多様化しています。
こうした動きは、英語を“科目”としてではなく、“実践的スキル”として重視する流れの表れです。
特に総合型選抜(旧AO入試)や推薦入試では、英語資格があるかどうかが合否を左右することも少なくありません。

英語圏以外から帰国する生徒の中には、現地で十分に学力や語学力を身につけていても、英語資格の壁に直面するケースが多くあります。
主な理由は次の通りです。
英検の海外会場が少ない:非英語圏では受験機会が限られ、試験日程も日本とずれる。 現地校の言語が英語ではない:フランス語・中国語・ドイツ語など、学習内容が日本の「英語力評価」と結びつかない。 TOEFL/IELTSは持っているが英検が必要:大学によっては「英検のみ可」と指定されるケースもある。 試験形式の違い:英検は“日本式”の筆記+面接構成のため、海外育ちの子どもには独特に感じられることも。 周囲の環境に“英語資格”への意識がない:非英語圏では「英語を勉強しよう」と声をかけてくれる人がほとんどいない。現地で必要とされるのは現地語でのコミュニケーション力で、英語資格は関係ないと感じてしまう。確かに、私たちが中国に住んでいた時は「英検受けなきゃ」なんて思ってなかったし、上の子なんて4年生で英検4級2回も落ちたし…
4級2回落ちても、特に危機感もありませんでした。
タイ・バンコクの日本人学校に通っていた中学2年生のAさん。
現地では英語の授業はあったものの、日常生活は日本語中心。
帰国後、志望校の帰国子女枠の出願条件に「英検準2級以上」と書かれていて、初めて“資格の壁”を意識しました。
実際、非英語圏では「英語を頑張っている子」が目立たないため、“周りがやっていないから、自分もまだ大丈夫”と感じやすい環境です。
でも、日本の入試では、英語力をスコアや級で“証明”することが求められるため、帰国直前になって焦るケースも少なくありません。
我が家はアメリカに移って途中まで、日常的に英語を使う環境になったので「せっかくだから英検取っとく?」くらいの気持ちでいました。
真剣に「英検取得」に取り組んだのは、帰国受験を意識し始めて、学校を調べ始めてから…
英語圏にいてもこれほどスタートダッシュが遅かったのに、英語圏以外ならなおさら遅れがちになってしまう人が多いのは、正直仕方がないことなのかもしれません。
だって、現地の生活に慣れるのに精いっぱいで、帰国後のことなんか考えられなかったんです。
そして、英語圏以外では“日常的に英語が聞こえてこない”ことも大きな違いです。
英語を使う機会が少なく、現地語での生活に慣れていくうちに、「英語を勉強する必要性」を感じにくくなってしまうのです。
結果として、「非英語圏からの帰国=英語資格を取るタイミングを逃しやすい」という構図が生まれています。
非英語圏からの帰国でも不利にならないための準備とは?非英語圏からの帰国で「一番の落とし穴」になりやすいのが、準備のスタートが遅れることです。
英検やTOEFLなどの英語資格は、短期間で結果を出せるものではありません。
特に非英語圏では、日常生活で英語に触れる機会が少ないため、“帰国1年前から”では間に合わないケースが多いのが現実です。
帰国準備として英語資格を意識するなら、「帰国の約2年前」が最低ラインです。
この時期から英語学習を“日常習慣”として根づかせておくことで、試験対策にスムーズに移行できます。
英検は年3回しか実施されず、合格証発行にも1〜2か月かかります。
なので、2年前から準備を始めたとしても、実質勉強できる時間は1年半しかありません。
また、大学入試や帰国子女枠では「出願締切時点での合格証」が求められることも多いため、余裕を持って逆算しておく必要があります。
特に非英語圏では、英語を勉強しないのが当たり前の環境にいることが多い。
だからこそ、「帰国が決まる前」から意識して動く家庭ほど差がつきます。
非英語圏では、塾や英会話スクールの選択肢が少なく、英語に触れる機会そのものが限られます。
しかし近年は、オンラインを活用すれば日本と同じカリキュラムで学ぶことが可能になっています。
駐在中でも、英検・TOEFLなどの資格対策を家庭で進めることができます。
① 日米バイリンガル講師のいるオンライン英会話・英語スクールを活用する海外在住者でも受講できるオンライン英語スクールが増えています。
中でもおすすめなのが、日本の英語教育基準に沿ったカリキュラムを持つスクールです。
特に短期間でできるだけ効率よく英検合格を目指すなら、日本語が通じるバイリンガル講師をお勧めします。
英語資格取得には、割高なネイティブ講師は必要ありません。むしろ避けるべきです。
日本人バイリンガル講師だと、自分も苦労して英語を学んできた経験があるし、自分も帰国子女だという方も多いです。
KIRIHARAとクラウティは、英語書籍で有名な「桐原書店」と「学研」が母体。
なので、テキストも教え方も、適切で効率が良いのが評判です。
 どのスクールも、海外からでも受講可能・日本時間でレッスン予約可。
どのスクールも、海外からでも受講可能・日本時間でレッスン予約可。
渡航先の生活リズムに合わせて、無理なく続けられます。
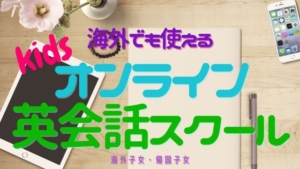
英語圏・非英語圏に関わらず、帰国前後に直面しやすいのが「思ったより英語資格の勉強が進まない」「何から手を付ければよいか分からない」という壁です。
ここで重要なのは、英検だけに固執せず、いまのレベルから合格ラインまでの最短経路を設計すること。
帰国子女に強いオンライン指導・総合型選抜専門塾なら、出願要件・日程・生活リズムまで含めた現実的なプランを「帰国子女の目線で」一緒に考えてくれます。

非英語圏の就学は、日本人学校・現地校・インターと本当に多様です。
英語が日常の子もいれば、日本語(あるいは現地語)中心で英語の時間が確保しづらい子もいます。
共通して言えるのは、日本の受験では英語力を“資格という形”で示す必要があるということです。
英語資格準備の開始は帰国2年前が最低ライン。
ここから耳と語彙、基礎文法を日常に組み込み、1年半〜1年前にかけて3級→準2級へ、直前半年で出願要件を確実に満たす――この逆算が、あとで慌てないいちばんの近道です。
また、短期間で効率よく合格をつかみ取るために「英検特化」や「帰国子女特化」「総合型選抜専門塾」をぜひ利用してください。
帰国子女枠受験も年々厳しくなってきています。
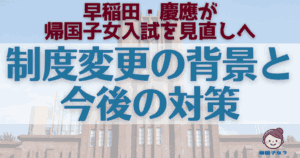
早稲田・慶應といった「帰国子女に人気の大学」が帰国子女入試を見直すことで、他大学もそれに追従するかもしれません。
なので、海外で生活してきた経験・海外で努力してきた経験を活かせるような道を、ぜひ探してみてください。
海外でも、帰国後でも——英語力を“可視化”しておく。
英語力が英語圏帰国者より低くても、必ず何か武器があります!
そこを伸ばして、有効に使えるように、まずはいろんな道を模索する意味でも「帰国受験に強いスクールの無料相談」を最大限利用しましょう。
それが、非英語圏からの帰国でも不利にならないための、いちばん確実な準備です。