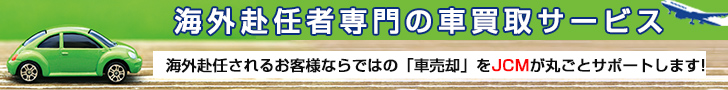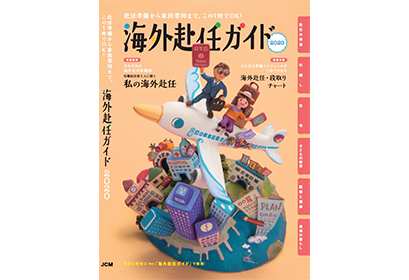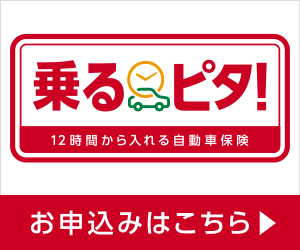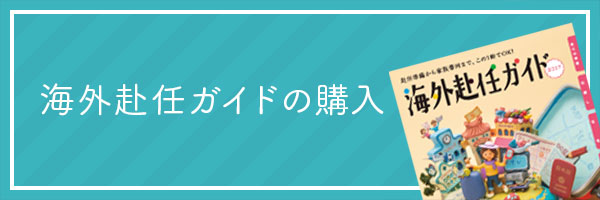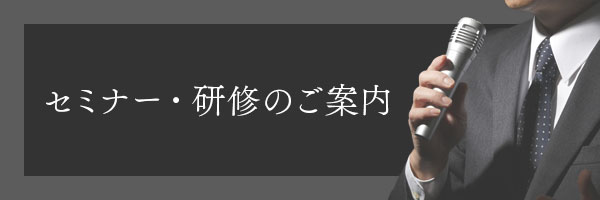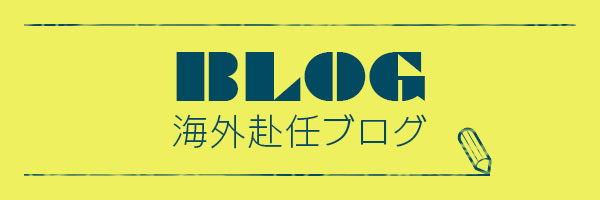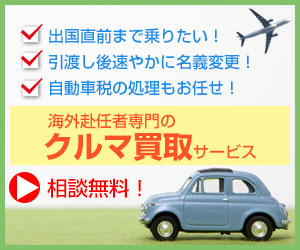前回は、私の決断を渋らせたものを大きく3つ紹介した中の1つめを紹介しました。
今回は2、3について具体的に話したいと思います。
まず前回のおさらいで、私が帯同をしぶった大きな理由は以下でした。
(細かく言ったらキリがないのでこのくらいに笑)
今の日本は保育園を一度辞めたら、簡単に戻ることはできない(日本の女性は一度仕事を辞めてしまったらなかなか復職できないという現実) 娘に食べ物のアレルギーがあり、日本で治療していた もし行くことになったら日本人幼稚園がないので、娘を現地の幼稚園(オール英語)にいれる必要がある
この記事では2、3について説明します。
娘の食物アレルギー問題
私の3歳になる娘には複数の食べ物のアレルギーがありました。
内容は小麦、卵(2歳で克服だけど要注意)、エビカニ貝類など。
アレルギーがあるということは、そのアレルギー物質の入った食品は食べられない、除去した食生活をおくらなければいけないということです。
特に小麦アレルギーに関しては、日本でもあまりに多くの食品(パン、麺、お菓子、ハンバーグ、餃子・・・・キリがない)に含まれており、大変苦労しました。
保育園では対応食を用意してもらうのはもちろん、誤食誤飲がないよう先生たちにも細心の注意を払ってもらう必要がありますし、
もちろんママ友やお友達にも。
スーパーでの買い物の際は原材料表を凝視してから買うのが日常でした。
また、日本では減感作療法や経口免疫療法と呼ばれる、アレルギー専門医のいる病院でのみ行われる、原因物質を少しずつ食べる食物アレルギーの治療も行っていました。
毎日家で継続して定期的に病院にも通う必要のある治療で、日本を離れるなら治療を中断するしかありませんでした。
病院、園の先生との密な連絡、ママ友やお友達の配慮、買い物やレストラン入店時の原材料確認・・・・
などが必要になる食物アレルギー。
これらは日本でも説明や理解に苦労することが多いのに、
英語のできない私と娘が海外にいけるわけないだろ・・・・・・・・・
と思ってしまったわけです。
食事は毎日3度あるものです。
食物アレルギーがある場合は、赴任場所のスーパーや食文化事情を事前にリサーチする必要があります。
旦那さんが出張に行ったときスーパーで食べられるものが日常的にそろうか確認してもらう、
現地にすでに住んでいる会社の奥さんのLINEを紹介してもらい、現地の買い物や園や病院でのアレルギーに対する認識などの質問をするなど、
旦那さんにも一緒に協力して情報収集してもらう必要があると思います。
ちなみに!今1ヶ月住んでみて感じていることは、
海外の方がアレルギーっ子には生きやすい環境
かもしれません。
なぜなら、「みんな同じものが食べられて当たり前」「園や小学校は全員同じメニューの給食」が普通の日本とは異なり
海外は宗教が違う人が入り混じり、それぞれ食べられない(好き嫌いではなく口にしてはいけない)ものがあって当たり前。
例えばカタール人の子供はイスラム教なので、豚肉やお酒を使用した料理は食べられないです。
また、健康志向やライフスタイルもそれぞれで、グルテンフリー(小麦不使用)、ビーガン(魚、肉、卵、乳製品などNG)などの商品が多く売られています。
みんな口にできないものがそれぞれあって当たり前なんですね。
いつかこれについては詳しくブログにのせたいと思います(^^)
というわけで来てから気が楽になっていますが、
こちらに住むか住まないかの決断を迫られていたときは、このような雰囲気を体感できていなかったので食物アレルギーはかなり悩ませる問題だったのです・・・
英語デキナイ問題
では私の決断を渋らせた最後の一つです。
はい、私は英語ができないんです(現在自己流勉強中)
できないというか、大学受験以来使っておらず、受験時も英語はどちらかというと苦手科目だった。
なんとか聞き取れるけど、口から英語が全く出てこないタイプですね。
カタールは病院も園もタクシーもスーパーもすべて、アラビア語か英語です。
英語ができる夫は平日は仕事でいないので頼りになりません。
一人ならまだしも、子供を連れて・・・
絶対無理!!!!!
と思いました笑
でもこれもまたいつかブログに詳しくまとめたいのですが、
・自分のスマホに翻訳アプリをインストールする
・タクシーはウーバー(アプリ上で送迎場所の指定や支払いができるもの)を利用すること
・文にしなくても単語を言うだけで意外と伝わる
あとは自分の生活圏内で必要な英語が自然と見えてきて、覚えるようになります(園の先生との会話やちょっとした挨拶など)
問題なのは、
自分のことよりおしゃべり大好きな3歳娘のことが心配で心配でなりませんでした。
やっと日本語がサマになってくる3歳で、特に女の子だと小さい頃から「おしゃべり」がお友達との遊びのツールなんですよね。
もともとママと離れるのも得意ではない内弁慶な娘が、先生ともお友達とも言葉が通じない園にすっと馴染める気がしなかったのです。
翻訳アプリや辞書に助けられる大人とは違い、子供はママと離れて、さらに何のツールも使わず自力でなんとかしなければいけないわけです。
「子供はすぐ慣れるよ!」と周りは言いますが、
その「慣れる」までに子供たちも多くの葛藤や孤独、努力でやっとやっと慣れるのです
(何を隠そう、私は帰国子女。※英語圏でなかったので英語力はゼロ)
また、帰国子女というと響きは良いですが、
現地の学校や英語に慣れたと思ったら、日本に帰国・転校など
慣れたら転校、また慣れない学校生活やお友達つくりを繰り返させてしまう可能性があります。
その苦労を知っているだけに、
日本で保育園から帰ってきて、その日にあったころやお友達とおしゃべりしたことを嬉しそうにマシンガントークする娘を見るたびに心が締め付けられる想いで悩んでしました。
・・・・
以上のように、こんなに悩んでいたのに結局今こうやって赴任先についてきた決断へのきっかけを次の
私が仕事辞めて、夫の赴任先に帯同した話③決断編
に綴りたいと思います(^^)