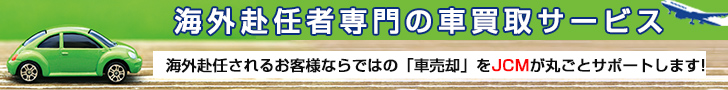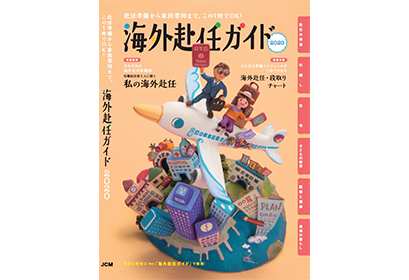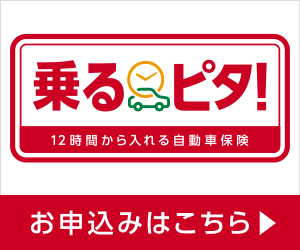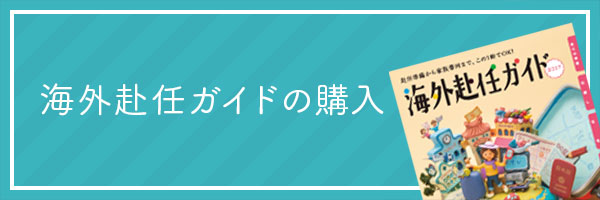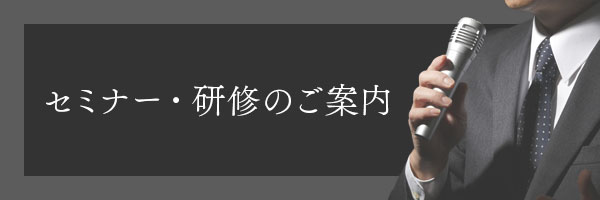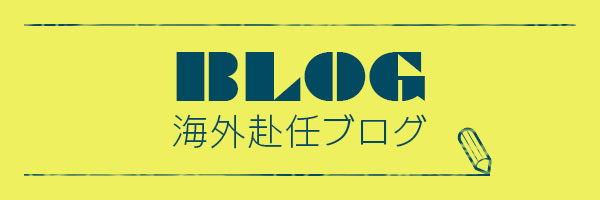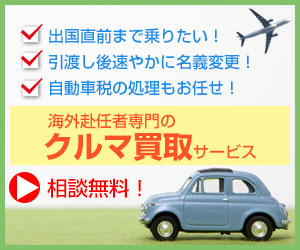3月8日の朝9時。いつものように勤務先のセキュリティゲートの列に並んでいると、人の流れに逆らって外に出てくる輩がいた。リトアニア人の同僚である。
「ずいぶん早い退社だね」と冗談を言うと、「いや、重要ミッションなんだ。これから花を買うんだよ」。
なんだそりゃ、と首を傾げた私はまったく野暮天で、実はこの日は International Women's Day(国際女性デー)なのであった。国連が定めたというこの記念日には、男性が日頃お世話になっている女性にお花を贈る慣習がある。同僚は、課内の男性陣を代表して、紅白のバラを買いに出かけるところだったのだ。
ウィーンには花屋(Blumenladen)があちこちにある。たいていの駅前にはあって、東京でいえば立ち食いそば屋くらいの頻度だろうか。「富士そば」としての花屋さん。
売るお店が多いのは、つまり買うお客が多いということだろう。どのお店も、わりに朝早くからやっている。通勤の途中で買っていく人も結構いる。オフィスに飾るためか、それともちょっとした人に贈るためか。
花束を小脇に抱えている人というのは、見ていてなかなかいいものだ。
背筋の伸びたお兄さんでも、物腰柔らかなお婆さんでも、サングラスをかけたマフィア風のおっさん(というのは前述の同僚のこと)でも、ひとつ花束を手にするだけで、不思議に「絵」になるものがある。
私の息子も、ときどき幼稚園にお花を持っていく。教室に添える花々を、児童が持ち回りで準備する決まりなのだ。
小さな花束を携えて、息子は大声で歌いながら往来を歩く。でも幼稚園に着くと、なぜだか急に静かになって、たくさん練習したはずの「Would you like flowers?」のフレーズが、どうしても口から出てこない。花束を抱えて、うつむいて立ちすくむばかりである。
その姿を見て私は、ああ、いいなあ、これは「絵」になっているなあ、と感心してしまう。
花のある暮らしには味わいがある。ウィーンに来て、はじめて私はそう思うようになった。
しかし、ウィーンにあるのは良い花屋ばかりとは限らない。
あれはまだ暖かさの残る秋の日、自宅の近くのケルントナー通りを歩いていると、お姉さんが満面の笑顔で私にチューリップを渡してくる。「何かのキャンペーンかな?」と、作り笑顔で花を受け取ったのが失敗だった。お姉さんのスマイルはたちまち消えて、「Donation!」と右手を突き出してくるのであった。
やむなく1ユーロ硬貨を渡したが、「Not enough!」「Donation, more!」と、お姉さんの追求は揺るがない。眉毛がどんどん吊り上がってくる。「それなら花は要らないです。返します」と言っても取り合わない。「Donation for what?」と訊いたら、「Donation for Donation!」と逆に怒られた。寄付のための寄付。もはや禅問答の世界である。
結局、合計で4ユーロも取られてしまった。
お金を損したことよりも、お姉さんのテンションに押し切られた敗北感に打ちひしがれて帰宅すると、私の妻も同一人物にたかられていたことが判明した。「ドネーションお姉さん」は、我が家の周りを活動拠点としていたのである。
けれども話を聞いてみると、奥さんは「ドネーションお姉さん」をうまく振り切ったということだった。「これは何のためのDonationなのか明らかにされたい」と問い続けたところ、ついに「Donation.... for me...」との言質を得たという。
私のための寄付。それはもう寄付ではなく、たぶん別の何かだ。もちろん妻は支払わない。妻はお姉さんに勝利し、お姉さんは私に勝利した。家族全体では一勝一敗の戦績だ。そして、しおれたチューリップを手にした私の立場はどこにもなかった。その姿はあまり「絵」にはならなかっただろう。
ということで、これからウィーンを訪れる方は、花の押し売りには気をつけてください。